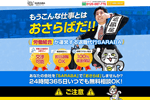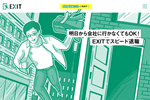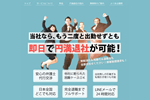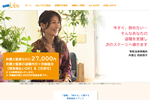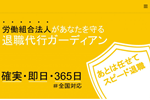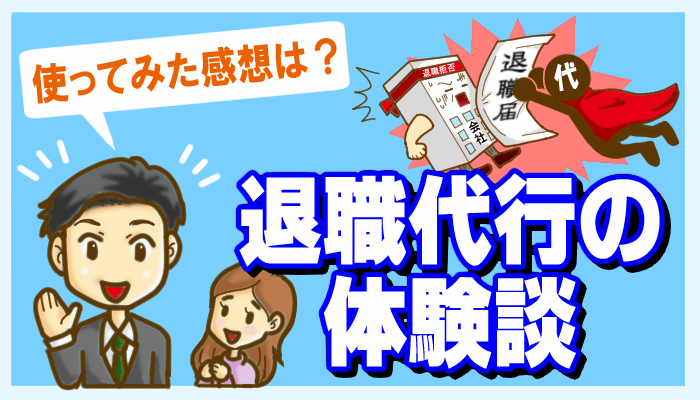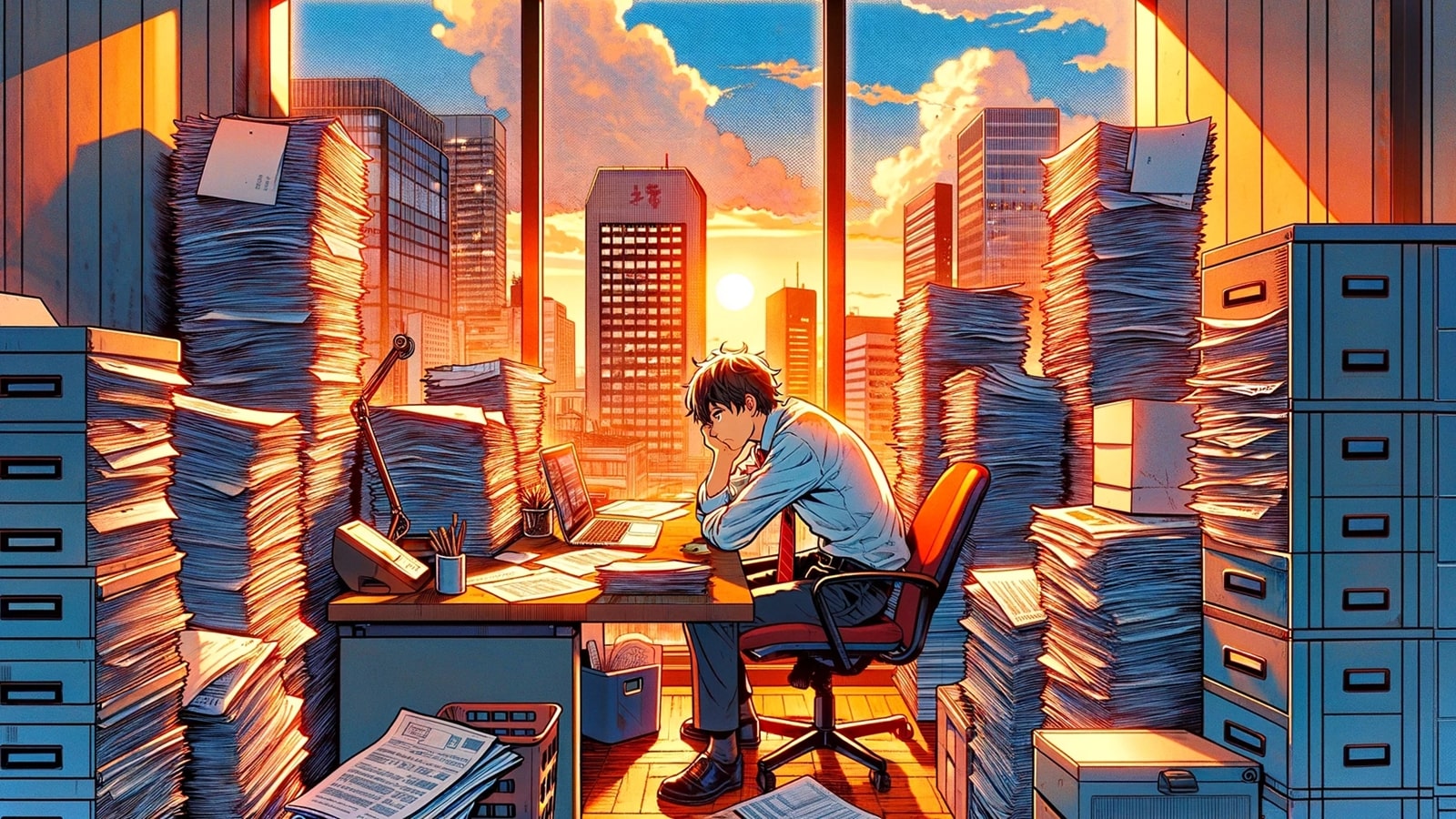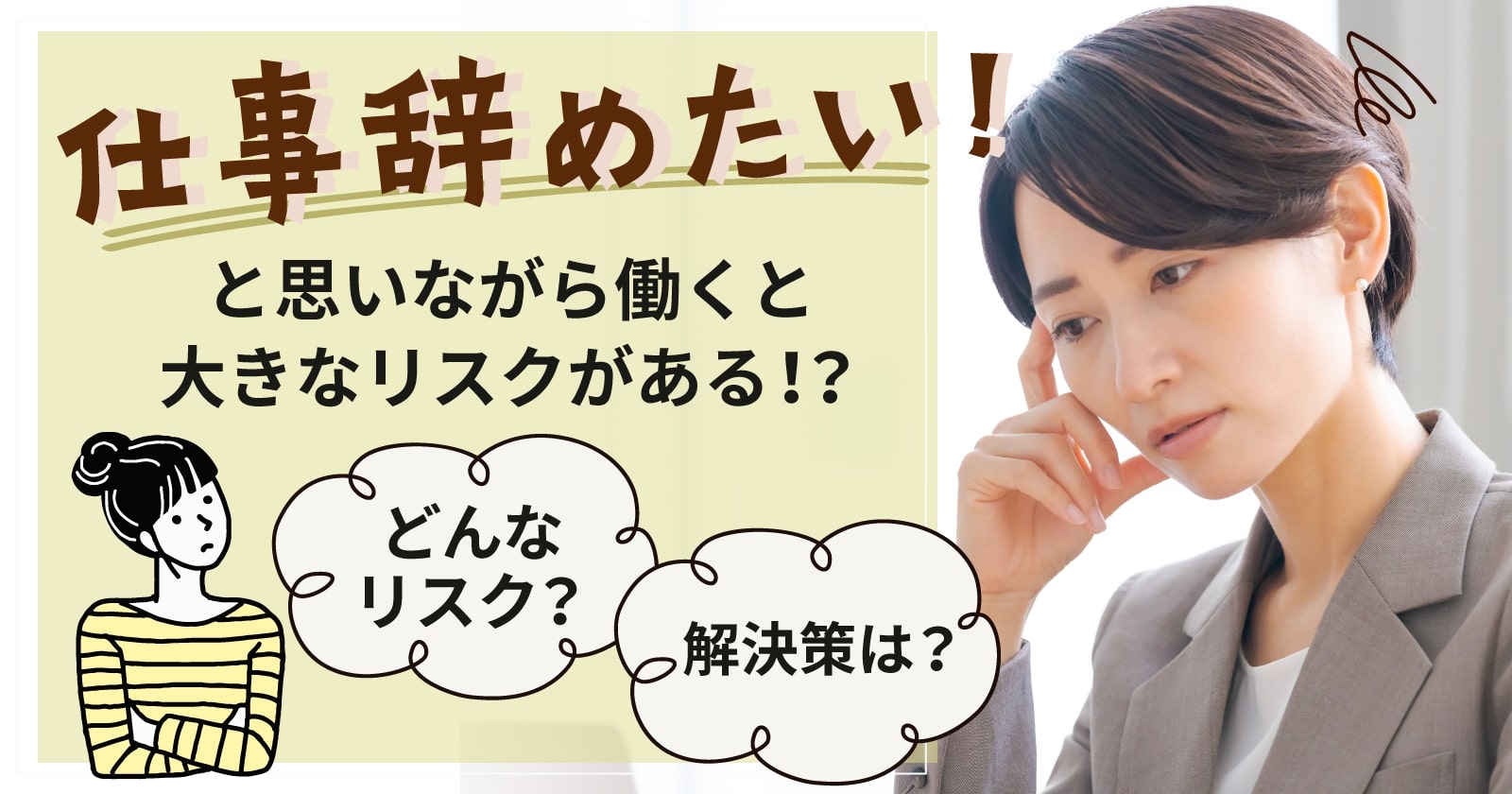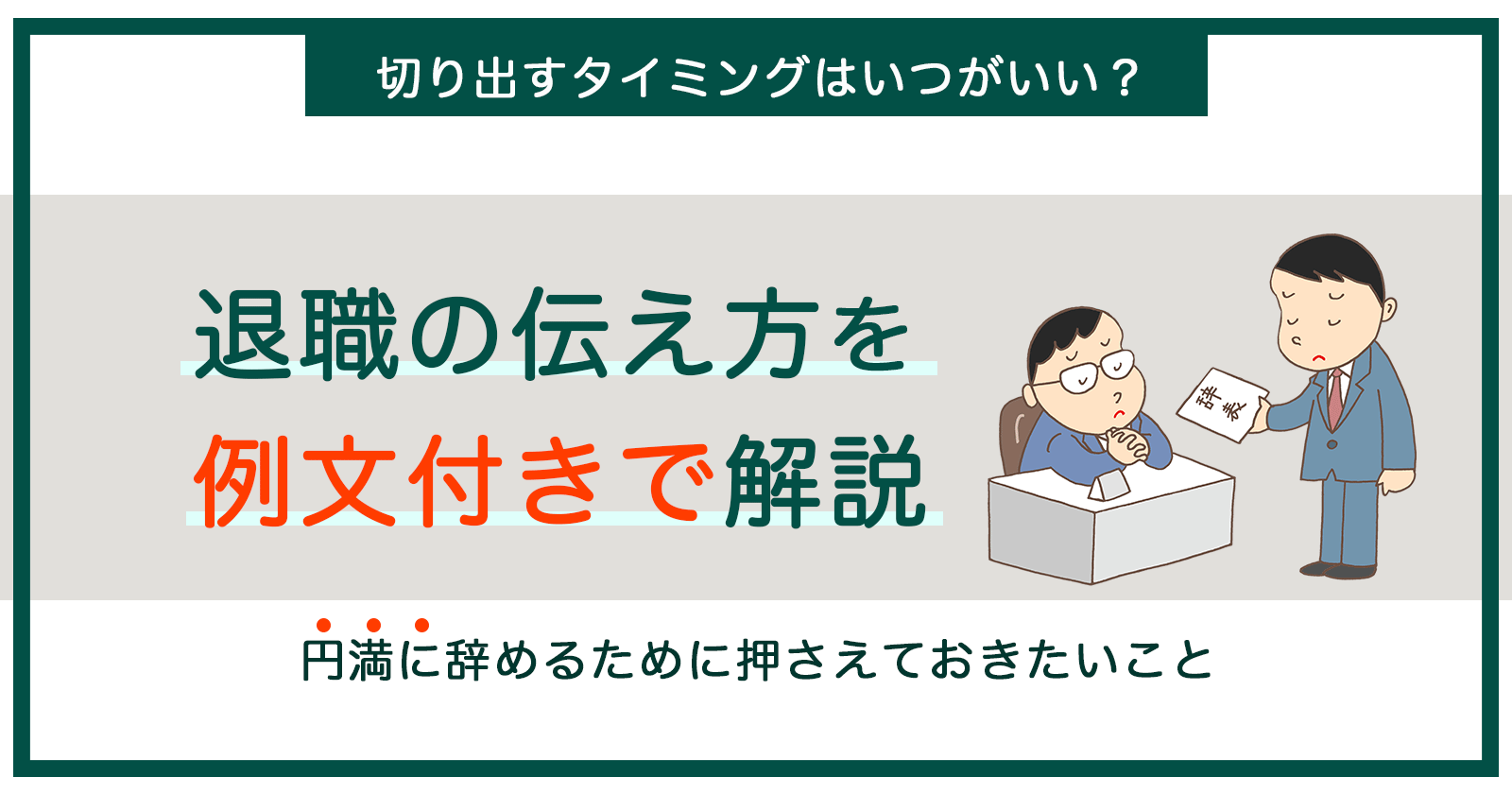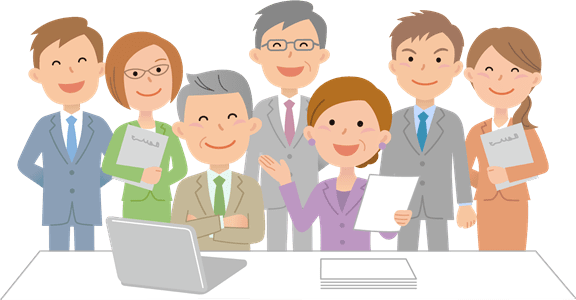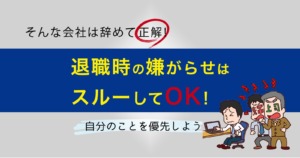会社を辞めると決断したものの、退職を言い出すタイミングや伝え方に、悩んでいる方も多いでしょう。
転職を成功させるためにも、できるだけ円満に会社を辞めて、気持ちよく次のステージに進みたいですよね。
会社を円満に退職するためには、
- 次に進むべき道や時期をはっきりさせること
- 現職に迷惑をかけないタイミングで、退職を伝えること
- 慰留する隙を与えないこと
上記の3つを押さえておくことが重要です。
この記事では、退職を伝える際のポイントについて、言い出すタイミングや退職理由の例文などを解説しています。
某メーカーの人事担当として約20年、さまざまな退職事例を目の当たりにしてきた筆者が、体験談を交えながらわかりやすくお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。
仕事を辞めると言うタイミングはいつがいいのか?

退職を申し出るタイミングは、1~2ヶ月前までに伝えるのがべストです。
退職する時期を明確にしておくことで、退職をよりスムーズに伝えることができます。
会社や上司に納得してもらうために、以下の3点について、しっかり準備をしておきましょう。
転職活動をどうするのかによって、退職を伝えるタイミングは変わる
退職を申し出るタイミングは、「転職活動をどのようにおこなうのか?」によっても変わります。
在職中に転職活動をする場合
在職中に転職活動をするのであれば、次の転職先へスムーズに入社できるように、
内定獲得まで、どれくらいの期間が必要になるのか?
上記をある程度予測して、引継ぎ期間との兼ね合いを考慮しながら、退職を申し出るタイミングを決めましょう。
退職を申し出るタイミングで、次に進むべき道が決まっていれば、

もう引き留めるのは難しそうだ…
会社や上司はこのように受け取るので、より納得してもらえる退職の伝え方になるはずです。
ですので、転職目的で退職をする場合は、退職を伝える前に転職活動を行なうべきといえます。
退職した後に転職活動をする場合
退職した後に転職活動をする場合は、退職するまでの期間が長引く可能性があります。
経済的に余裕がある方なら、



退職してから、じっくりと転職活動したい…
と考えている方もいるかもしれませんね。
しかし、転職先を決めずに退職の話を持ち出した場合は、



業務が落ち着いたら退職を認めるから、それまでは業務に専念してくれ
このような引き延ばし策を、会社がしてくるかもしれません。
結局、そこからズルズルと引き延ばされてしまい、



なんだかうやむやにされて、退職できそうにないぞ…
こういった状況になりかねないのです。
また、退職後に転職活動をするということは、
- 転職活動が長引いてしまう
というリスクも考慮しておく必要があります。
退職をした後の転職活動が長引いてしまうと、マイナスになる点が多いので、求人の動向などを見極めてながら、慎重に退職時期を見定めましょう。
業務の引き継ぎ期間を確認する
とくに中高年の転職であれば、役職者であったり、管理業務を担っているケースが多いので、



どれくらいの引き継ぎ期間を設ければ、周りの人々への迷惑を最小限に抑えられるのかな?
ということについて、しっかり確認しておきましょう。
引き継ぎ期間をしっかりと想定しておけば、会社や上司にも納得して貰いやすくなります。
転職活動をするうえでも、引き継ぎ期間は必ず質問される内容なので、事前に把握しておくようにしてください。
ただし、引き継ぎ期間が長すぎると、応募先企業から敬遠される可能性が高くなってしまいます。
引継ぎの期間は、長くても2ヶ月程度に収まるように準備しましょう。
なかには、



2ヶ月では、とても引継ぎが終わらない…
という方もいるかもしれませんね。
この場合は、引き継ぎに関する資料やマニュアルをしっかりと作成して、
迷惑の掛かる部分が、最小限になるよう心掛ける
上記の配慮をしたうえで、2ヶ月以内に終わらせましょう。
バランスを保つことは難しいですが、
- 現職の引き継ぎ期間
- 転職先に入社まで待ってもらう期間
この両者を頭に入れて行動することが、スムーズに退職するためのポイントです。
退職を伝える時期は、民法の定めより就業規則を守る
退職を伝える時期について、押さえておきたいポイントは、
会社で制定されている就業規則をふまえる
ということです。
就業規則には、退職を申し出る時期が必ず規定されています。
短い場合は2週間前、長くて2ヶ月前といったケースもありますが、1ヶ月前としている会社がいちばん多いです。
就業規則で規定されている、退職を申し出る時期を必ず守るようにしましょう。
民法上では、
2週間前までに申告をすれば、会社を退職することができる
とされているのですが、円満退職を望む場合は、社内規定を守って行動するべきです。
ただ、たとえ就業規則を守ったとしても、



引き継ぎ期間が十分ではないんだけど…
会社からこのように思われてしまうと、退職はできても、円満退職とは程遠いものになってしまいます。
退職を伝える際には、就業規則の遵守と引継ぎ期間のバランスを見ながら、タイミングよく行動することが重要です。
円満に辞めるための退職理由の伝え方
円満に会社を辞めるためには、
退職理由をどのように伝えるのか?
上記がとても重要なポイントです。
退職の話がスムーズに進まないと、転職活動にも影響する可能性があります。
また、退職理由として今までの不満を言ってしまえば、円満に辞めることは難しくなるでしょう。
ここでは、退職理由を伝える際の注意点として、以下の3つのポイントについてご紹介します。
退職理由で会社への不満を言わないこと
「退職理由」は会社から必ず聞かれることであり、答え方次第で円満にも険悪にもなります。
退職を決めたのですから、
というのが正直なところでしょう。
だからといって、退職理由として会社への不平不満を、ストレートに伝えてしまうことはNGです。
不満をぶつけたところで、今後のプラスにならない
退職理由で会社への不平不満を伝えると、退職を相談・調整してもらう上司が、感情的になってしまう可能性があります。
その結果、



退職の話が前に進まなくなってしまった…
ということでは意味がありませんよね。
退職したあとも、上司を含めた会社の人たちに、二度と会わないとは限りません。
業界が同じであれば、今後も関わる可能性もあり得ますし、退職の仕方によっては、自分の人脈となってくれるかもしれないのです。
とくに待遇面や環境面を退職理由にした場合は、



改善をするから、退職を思いとどまってくれないか?
上記のような引き留めにあう可能性もあります。
退職理由を伝える際に、



どうせもう辞めるんだし、思うことは言っておこう…
こういった気持ちで不満を話したところで、多少はすっきりするかもしれませんが、自分のプラスになることはあまりないのです。
ポジティブな印象を与えるように心掛ける
円満に辞めるためにも、不満を口に出さずに、



これまでありがとうございました
と感謝を伝えた方が、物事がずっとスムーズに進みます。
もしかしたら、退職後の活躍を応援してくれるかもしれません。
もちろん、嘘をつく必要はありませんが、
- やりたいことがある
- キャリアアップしたい
上記のように、できる限りポジティブな印象を与えられるような言い方に変えて、退職理由を伝えるようにしましょう。
ネガティブな退職理由は言い方を変える(例文あり)
ネガティブな退職理由の例としては、
- 給料が安い
- 評価への不満
- 上司のパワハラ
- やりたい仕事をやらせてもらえない
こういったものが挙げられます。
もし、ネガティブな理由で退職を伝える場合は、
- ネガティブな退職理由を、オブラートに包んだ形で表現する
- その現状を変えるために、転職先を決めた
上記のようなストーリーにして伝えれば、円満退職に近づけることができるでしょう。
ネガティブな退職理由の「言い方を変える」具体例として、以下を参考にしてみてください。
退職理由の例文1:仕事がつまらない、飽きている
大手の安定感が魅力で入社したが、ルーチンワークで仕事がつまらないし、身につくスキルが限定的で正直飽きている
今までは大手のブランド力に助けられ、恵まれた環境だったことに感謝しています。
これからは新たな環境で仕事の幅を広げて、キャリアアップしたいと思い退職を決意しました。
退職理由の例文2:いまの仕事はやりたいことじゃない
本当は〇〇業界で働きたかったが、採用をもらえずに諦めた。今いちど将来を考えると、今の仕事はやりたいこととは違うので、5年後10年後もここで勤めたいとは思えない。
今の仕事や環境に不満はなく、やりがいも感じていますが、いちど諦めてしまった〇〇の業界に未練があり、チャレンジするのは今しかないと思い退職を決意しました。
退職理由の例文3:やりたい仕事をやらせてもらえない
持っている資格を活かせる経理部署への異動を希望していたが、社内的に異動できる雰囲気ではなかった。
以前から、保有している資格を活かして、経理の仕事がしたいと考えていました。
現状はその仕事ができておらず、部署異動を申し出ようと考えたのですが、私のわがままを押し通すと、会社にも迷惑を掛けると考え、経理の仕事ができる企業へ転職を決めましたので、退職させて頂きたいと思います。
退職理由の例文4:評価に不満がある
いまの仕事や職場は好きだけど、評価されていないことに納得がいかない。
今の仕事は大好きで、職場の雰囲気や周りの人にも恵まれていたと思います。
ただ、なかなか思うような評価を得られなかったことから、「職場の足を引っ張っている」「この仕事に向いていないのでは?」という思いを抱き続けてきました。
好きな職場の皆さんにこれ以上迷惑を掛けたくない思いと、定年までにもう一度、新たな環境で挑戦したいと考え、退職させて頂きたいと思います。
家庭の事情で退職するときの伝え方(例文あり)
家庭の事情による退職の場合は、会社がいくら残って欲しいと願っても、会社は詳細な内容まで深く突っ込むことができません。
会社側もやむをえず、納得せざるを得ないでしょう。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 両親など身内の介護や看病
- 家業を継ぐ など
家庭の事情による退職の場合は、やむを得ない理由であるため、会社側にほぼ認めてもらえるはずです。
ですので、できるだけ速やかに、正直に伝えるようにしましょう。
先日、父親が倒れ、介護が必要な状況となってしまいました。
父親は古くから会社を経営しており、その会社を存続させるためには、私が家業を継がざるを得ません。
今の仕事や生活に十分満足していたため、非常に残念ですが、退職させて頂きたいと思います。
退職の意思は、直属の上司に伝えよう


退職の意思を伝える相手についてですが、まずは直属の上司に伝えるようにしましょう。
直属の上司に伝えることによって、会社を退職するための正規ルートに沿って、退職手続きを進めることができます。
スムーズな退職のためには、上司の納得が不可欠
直属の上司に伝えるべきとわかっていても、



直属の上司が原因で、退職をしたいんだけど…
という思いから、人事部に直接相談したり、さらに上の上司に申し出をしようと考えている人もいるかもしれません。
しかし、直属の上司に相談していないと、
- しっかりと話を聞いてもらえないことが多い
というのが実際のところです。
退職手続きに関するさまざまな調整は、上司の協力なくして円満には進みません。
まずは上司の理解を得ることを心がけましょう。
対面で話して伝えること
退職というのは、会社と自分の双方に重要なことなので、
メールなどで伝えるのではなく、上司と対面で話して真剣に伝える
というのが鉄則です。
上司と話す際には、会議室などで二人で話せる時間を確保してもらいましょう。
そのためにも、繁忙期や多忙な曜日・時間帯を避けて、じっくり話せる段取りをしてください。
上司以外には口外しないのがマナー
退職の意思は、上司以外には口外しないようにしてください。
社内で正式に公表される前に、



〇〇さんが辞めるらしいよ…
といったうわさが一人歩きしてしまうと、現場や同僚の間で混乱が生じる可能性もあります。
また、直属の上司を飛び越えて、さらに上の役職者へ退職の相談をすることも、基本的には避けておくべきです。
別の人から上司へ伝わってしまうようなことがあると、上司への心象にも影響しますし、トラブルになりかねません。
どうしても、自分から直接伝えたい人がいる場合は、その旨を直属の上司に相談したうえで、上司の判断を仰ぎましょう。
退職を伝えるときに、押さえておきたいこと
上司に退職の意思を伝える際は、



もう後戻りはできない!
このような強い意思をもって、面談の場にのぞみましょう。
いちど退職の意思を伝えてしまうと、簡単に取り消したり、前と同じ状況に戻ることはできません。
上司へ伝える際のポイント
いざ退職を伝える場にのぞもうとすると、この上ない緊張感が押し寄せてくるかもしれません。
自分の今後の人生を左右する瞬間ですから、緊張するのは当然のことです。
上司にじっくりと話を聞いてもらうためにも、上司の仕事がひと段落した時間帯を見計らって、



相談させていただきたいことがあるので、別室で話を聞いてもらってもいいでしょうか?
このような形で時間を取ってもらいましょう。
上司に退職の意思を伝える際は、「退職を考えている」という抽象的な表現は避け、
「退職させて欲しい」という強い意志
上記がしっかり伝わるような切り出し方をしてください。
抽象的な伝え方としてしまうと、上司から強く慰留される可能性が高まります。
引き留められても、退職の意思を貫こう
退職を申告した際には、よほど人が余っている状況でもない限り、引き留められることがほとんどでしょう。
ただ、いちど退職を決断したからには、引き留めを断る強い意志が必要です。
もちろん、一方的な態度では険悪になりかねません。
まずは引き留めてくれたことへの感謝を述べながら、退職の意思が固いことを伝えましょう。
上司が退職を引き留める理由は、さまざまなことが考えられます。
- 会社にとって必要な戦力だから
- 人員募集には、経費や育成期間が必要だから
- 描いていた運営プランが狂うから
理由はどうであれ、上司が真剣に引き留めてくれれば、悪い気はしないでしょう。
責任感が強い人なら、退職することが申し訳ない気持ちになるかもしれません。
しかし、たとえ退職者がでたとしても、会社は変わらず運営されていきますし、あなたが辞めても倒産することはないのです。
せっかく覚悟を決めて上司を呼び出したのですから、



上司に納得してもらうまで、粘り強く話し合うぞ!
という強い意志を持ってのぞみましょう。
退職の撤回にはデメリットが多い
上司から引き留められて、すぐに退職を思い留まるくらいなら、はじめから退職を切り出すべきではありません。
なぜなら、退職の撤回にはデメリットが多いからです。
いちど退職を申告すると、上司からは、



いったんは思い留まらせたけど、またいつ辞めると言い出すからわからないな…
このように思われてしまう可能性があります。
今後は責任あるポジションへのキャリアアップに、影響が出てしまうかもしれません。
また、口頭では待遇や環境面の改善を提案してくれたとしても、本当に実現するかは不確定です。
たとえ改善されたとしても、また別の理由で、



やっぱり退職したい…
このような気持ちになったときに、さらに退職が切り出しにくくなってしまいます。
退職の意思を伝えるということは、会社にとっては相当に重い通告であり、切り出してしまった以上、撤回してもデメリットが多いのです。
したがって、退職を決断するまでに、
自分の叶えたいことが、いまの会社で実現できるのか?
このような可能性について熟考するようにしてください。
そのうえで、新たな道に進むと決めたのであれば、いちど伝えた退職希望を撤回するべきではありません。
退職願(退職届)は、上司との面談後に提出する
退職願は、上司へ退職の意思を伝えて、退職日の調整が済んだ段階で上司へ提出するようにしましょう。
事前の相談なく退職願を渡したり、一方的な希望で退職日を書いてしまうと、



事前に相談もなく一方的だな…
このように思われて、関係がギクシャクしてしまうものです。
上司とよく話し合って、双方が納得できる退職日で退職願を提出することで、円満退社につながります。
退職願の書き方やテンプレートは、以下の記事でご紹介していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
会社から強く引き留められた場合はどうする?


いまは人手不足の会社が多いので、仕事を覚えてきっちりこなしている社員が退職することは、会社にとっても大きな痛手です。
場合によっては、
会社から退職を強く引きとめられる
というケースもあります。
もし退職を強く引きとめられた場合は、以下の点を押さえて冷静に対応しましょう。
期限をしっかり決めて、手続きを進める
自分の意志がしっかり転職に向かっていて、気持ちに揺らぎがないときは、感謝の気持ちを伝えつつ、



退職の意思は変わりません
とはっきり伝えましょう。
会社側は辞めてほしくないので、



何とか繁忙期まで引っ張って、辞めづらくしよう…
こういった引き延ばし作戦をしてくる場合があります。
会社側の嫌がらせを回避して、転職先に影響が出ないようにするためにも、退職期限をしっかり決めて、手続きを進めてることを意識してください。
なぜ退職すると決めたのか、もう一度しっかり考える
もし引きとめられて、心が揺れ動くようなら、
- いまの会社にまだ未練がある
- 仕事や同僚などに対する情が深い
このような気持ちがあるのかもしれません。
会社側は、あなたのそういった気持ちに付け込んで、なんとか退職時期を引き延ばそうとしているのです。
引き留めで心が揺れる場合は、



なぜ退職しようと決意したのだろうか?



辞めずに残るという選択肢はあるのかな?
といったことを、もういちど冷静に考えてみましょう。
しっかりとした、次のステップへの意志が固まっているのなら、どんなに引きとめられても、辞めることを優先させるべきです。
会社側がその決意を妨害してくるようであれば、無理に円満退社にこだわり過ぎる必要はありません。
円満退社が難しそうなときは「退職代行」もあり
基本的には、責任をもって退職の手続きを進めるべきですが、
- 上司に相談しても拒否されてしまう
- 周りの反応が怖くて言い出せない
- 精神的に辛いのですぐ辞めたい
上記のように、どうしようもないというケースであれば、退職代行サービスを利用するのもひとつの方法です。
退職代行を利用するメリットとは?
退職代行とは、労働者本人の代わりに弁護士や代行業者が、会社へ退職の意思を伝えるサービスのこと。
退職代行を利用することで、
- 精神的な負担を減らせる
- 即日退職できる
- 正当な権利を行使できる
上記のようなメリットがあります。
精神的な負担を減らせる
自力で退職を進める場合には、上司や同僚への報告、業務の引き継ぎなど、さまざまな手続きが必要です。
退職理由に関して、周りからの理解が得られそうにない場合は、
- 強い引き留めにあう
- 嫌がらせを受ける
このようなリスクもあるでしょう。
しかし、退職代行を利用すれば、労働者本人は会社と直接やりとりをする必要がありません。
代行業者が手続きを淡々と進めるだけになるので、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
即日退職できる
即日退職できるのも、退職代行を利用するメリットの一つです。
本来、民法上では、
ということが定められています。
民法第627条
出典:Wikibooks
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
しかし、実際には、



繁忙期は避けてほしい



後任が決まるまで待ってほしい
このような会社都合の理由で、退職日が先延ばしにされてしまうことも少なくありません。
退職代行を使う場合は、退職までに必要な2週間の期間を有休消化や欠勤扱いとすることで、
退職代行が会社に連絡した日から会社に出社しない
という対応が可能になります。
ハラスメントを受けている場合や、体調が悪化している場合など、



1日でも早く会社を辞めたい…
という場合には、心強い味方になってくれるでしょう。
正当な権利を行使できる
最近では、弁護士や労働組合が退職代行サービスに乗り出すケースも増えているので、
- 残業代の未払いがある
- 有休消化を拒まれる
といった労働問題に対しても、代理人として責任をもって対応してもらえます。
退職代行を依頼すると費用が発生しますが、初回相談は無料です。
会社側への交渉ごとがある場合も、対応可能かいちど相談してみることをおすすめします。
- 【安さで選ぶなら】退職代行EXIT
民間企業が運営。業界のパイオニアが最安値に挑戦中。リピート割がお得。20,000円(追加料金なし) - 【会社と交渉したい】退職代行SARABA
労働組合が運営。24時間365日いつでも相談OK。即日の退職連絡も可能。24,000円(追加料金なし) - 【弁護士に任せたい】
弁護士法人が運営。弁護士退職代行の老舗。会社との交渉や請求、万一の訴訟対応もOK。55,000円~
退職代行を使っても大丈夫?
そうはいっても、「退職代行」と聞くと、



会社の同意がないまま、無理やり辞めていいのだろうか…
と思う人もいるかもしれませんね。
そもそも退職は、労働者に対して法律で認められている権利です。
何らかの理由で辞めにくいという場合は、
退職を阻害している会社側の対応に問題がある
という場合が多いのではないでしょうか?
退職代行を利用することに、負い目を感じる必要はありません。
今では、
- 利用者の58%が30代以上、40代以上の割合は28%
- 40代でも34.8%の人が、退職代行の利用を検討
上記のような調査データもあるくらい、年齢や会社規模を問わず、退職代行は幅広く利用されています。
当サイトでも、実際に利用した人たちの体験談を数多く紹介しています。詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
まとめ:会社を円満退職するために必要なことは?
今回は退職の伝え方について、言い出すタイミングや納得されやすい退職理由の例文、退職を伝える際に押さえるべきポイントについてお話ししました。
会社を円満に辞めるためには、
- 次に進むべき道や時期をはっきりさせること
- 現職に迷惑をかけないタイミングで、退職を伝えること
- 慰留する隙を与えないこと
上記の3つがポイントとなります。
ただ、退職は多かれ少なかれ、周りの人に迷惑をかけることに違いはありません。
周りの人々に、笑顔で送り出されることが円満退職だと思うと、しんどくなってしまいます。
現職に対して、自分自身が悔いなく納得できる去り方ができれば、



それが円満退職だよ!
これくらいの感覚で退職を伝えるようにしましょう。
退職の意思をトラブルなく伝えるための、参考となれば幸いです。