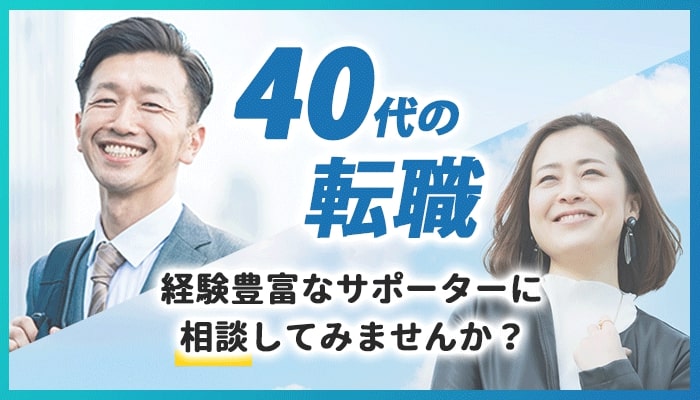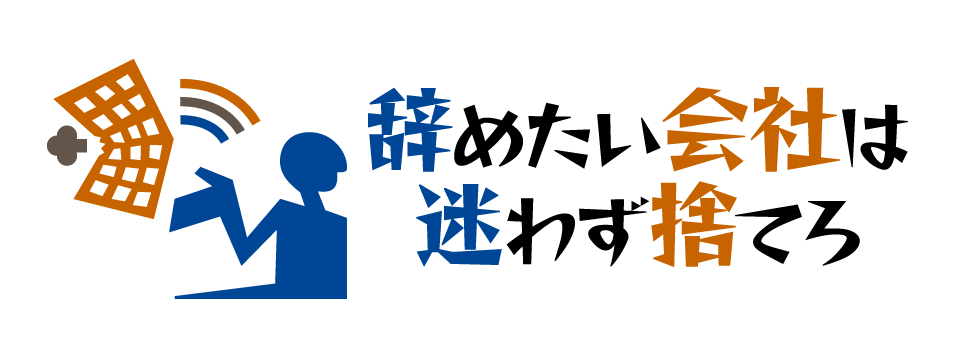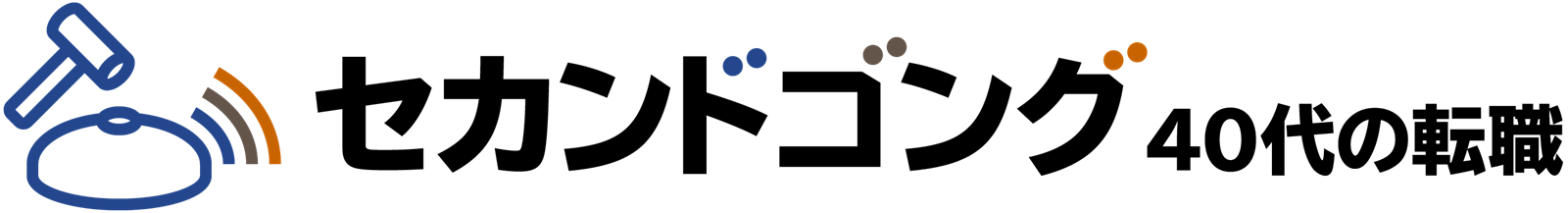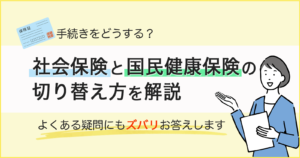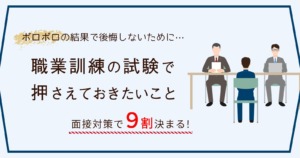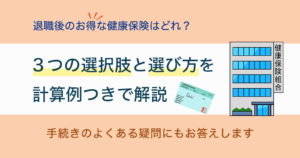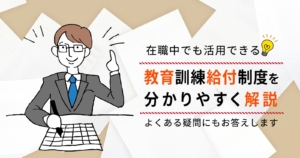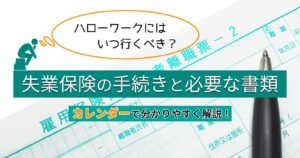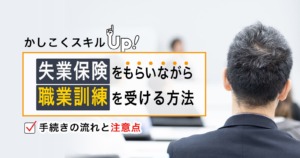社会保険から国民健康保険への切り替え方!国保のよくある疑問も解説
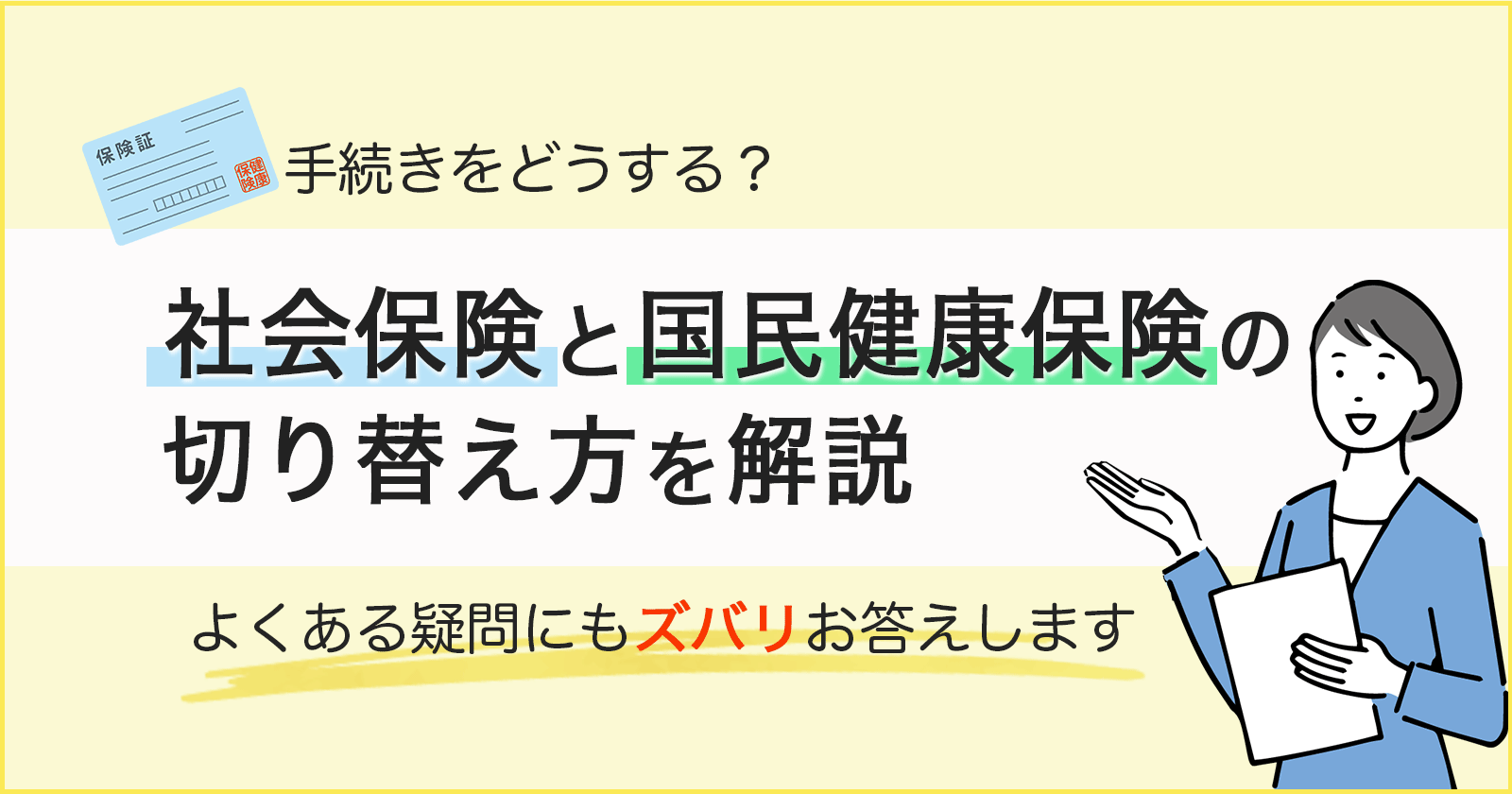
(執筆:五島 アツシ)
会社を辞めた場合に、社会保険から国民健康保険に切り替えるケースがあります。
しかし、実際に手続きをする場合に、

どこに、どんな書類を出せば良いのかよくわからない…
こういった方も多いのではないでしょうか?
とくにはじめて会社を退職したという方なら、分からないことだらけですよね。
そこで本記事では、国民健康保険の加入・脱退の手続きについて知りたい方に向けて、切り替え方法やよくある疑問についてわかりやすく解説しています。
かつて法務部や人事部に所属し、社会保険の手続きを行っていた筆者の経験にもとづいてお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。
なお、健康保険の基礎知識やお得な健康保険の選び方については、以下の記事でご説明していますので、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
退職後のお得な健康保険はどれ?選び方のポイントと比較方法を解説

やまもと社会保険労務士事務所
代表 山本 務
50代男性、東京都在住。大卒後はSE、人事労務業務に従事し、社労士試験合格後に50代で社会保険労務士として独立。元労働局総合労働相談員。労働相談、人事労務管理、就業規則、電子申請、給与計算が得意です。【特定社会保険労務士】
国民健康保険への加入・脱退が必要なケースとは?

日本では「国民皆保険制度」を採っていますので、必ず何らかの健康保険に加入しなければなりません。
国民皆保険制度とはどのようなものですか?
「国民皆保険」とは、病気のときや事故にあったときの高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民が公的医療保険に加入しなければならない、という制度です。
(中略)民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ず公的医療保険にも加入しなければなりません。
出典:郡山市ホームページ
退職する際、空白期間なくすぐに転職する場合は、新しい会社が健康保険の加入をしてくれるので、とくに手続きは不要です。
しかし、退職後すぐに再就職しない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険に加入する必要があります。
- 任意継続を行う
- 家族の健康保険の被扶養者になる
- 国民健康保険に加入する
健康保険は二重に加入することはできないため、脱退手続きが必要になることも…
ここでは、国民健康保険への加入や脱退が必要となるケースについてご説明します。
国民健康保険への加入が必要なケース
国民健康保険への加入が必要なケースは、以下のような場合です。
- 会社を退職し、任意継続も家族の健康保険の被扶養者にもならないとき
- 任意継続を行っていたが、継続後2年が経過したか、保険料未納によって資格を喪失したとき
- 家族の健康保険の扶養に入っていたが、その家族が退職して健康保険の資格を喪失したとき
- もともと国保に加入していて、他の市区町村へ引っ越すために脱退したとき
- もともと国保に加入していて、子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国民健康保険からの脱退が必要なケース
国民健康保険から脱退が必要となるのは、以下のような場合です。
- 再就職して、会社の健康保険に加入したとき
- 家族が再就職して、その健康保険の扶養に入ったとき
- 他の市区町村へ引っ越すとき
- 加入者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
国民健康保険は、市区町村ごとで加入する必要があるため、市区町村外に引っ越す場合にはいちど脱退して、引越し先で再び国保に加入する必要があります。
社会保険から国民健康保険への切り替え方
ここでは、社会保険から国民健康保険(国保)への、切り替え方についてご説明します。
難しい手続きではありませんが、必要な書類や期限がありますので、しっかり確認していきましょう。
退職から14日以内に国保への切り替え手続きが必要
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に、必ず切り替え手続きをおこなってください。
14日を過ぎても加入することはできますが、その場合は医療保険の給付が受けられないなど、不利益が生じてしまいます。
万が一のとき、しっかり給付が受けられるように、期限内に手続きを行いましょう。
期限内に提出するためには、必要な書類を準備しておくことが重要です。
次項の必要書類を確認して、会社が作成する書類を早めにもらえるように依頼しておきましょう。
国民健康保険への切り替えに必要な書類
社会保険から国民健康保険への切り替えに必要な書類は、以下のとおりです。
- 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険等資格喪失証明書など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑、通帳、キャッシュカード(口座振替ができる場合)
- 世帯主と加入者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
上記❶は、退職証明書や離職票でも問題ありませんが、念のため、お住いの市区町村の国保窓口Webサイトで確認することをおすすめします。
国民健康保険の申請先
国民健康保険の申請先は、お住まいの市区町村役所の国民健康保険担当窓口です。
地区市民センターやコミュニティーセンターなど、市区町村の出先施設では、申請可能な施設と申請できない施設があります。
Webページで、申請可能か確認してから出向いてみましょう。
国民年金の加入も同時に手続きしよう
国民健康保険の加入申請をおこなった際は、一緒に国民年金への加入手続きもおこないましょう。
多くの役所では、国保窓口の隣に国民年金の窓口がありますので、すぐに手続きすることが可能です。
国民年金の加入に必要な書類は、以下のとおりです。
- 退職日や厚生年金の資格喪失日を確認できる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証明書など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
- 年金手帳
在職時に会社で入っていた厚生年金の脱退手続きは、会社がすべておこなってくれます。
国民健康保険から社会保険への切り替え方

会社に就職した場合は、その会社の社会保険に加入することになります。
国民健康保険から社会保険へ切り替える場合の手続きは、以下のとおりです。
国保の脱退手続きをおこなう
就職をして、会社の社会保険に加入した場合は、国保脱退の手続きをおこないます。
社会保険への加入手続きは、会社がやってくれますが、国民健康保険の脱退手続きは自分でおこなう必要があるので注意してください。
以下の書類を持参して、お住まいの市区町村役所の国保窓口で、脱退手続きをおこないましょう。
- 会社の健康保険証
- 脱退する国民健康保険の保険証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
上記❶は、「健康保険資格取得証明書」などの「加入した日付がわかる証明書」でも、手続きは可能です。
ただ、念のため、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口Webサイトで、確認しておく ことをおすすめします。
なお国保の脱退も、社会保険加入から14日以内におこなう必要があります。
脱退が遅れても、とくに不利益があるわけではありませんが、市区町村側でムダな手間が発生しますので、やはり期限内に手続きを行いましょう。
国民年金の脱退手続きは不要
国保の脱退手続きは必要ですが、国民年金の脱退手続きは不要です。
就職した会社が厚生年金の手続きを行うと、年金事務所に連絡表が提出されて、自動的に国民年金の脱退手続きは完了します。
社会保険への加入方法
社会保険への加入手続きは、すべて会社が行ってくれます。
会社の指示に従って、年金手帳などの必要書類を提出すれば終了です。
ただし、家族を健康保険の扶養に入れる場合には、さまざまな書類が必要になります。
会社に必要書類を確認して、早めに提出するようにしましょう。
国民健康保険の手続きでよくある疑問にお答えします(FAQ)

ここでは、国民健康保険や社会保険などの保険切替時に、よくある疑問についてお答えします。
切り替え手続きを忘れた場合、14日を過ぎても国民健康保険には加入できる?
国民健康保険の加入期限である、「退職日の翌日から14日」を過ぎた後でも加入は可能です。
ただし、14日を過ぎてから加入しても、保険料は退職日の翌日から支払う必要があり、保険給付の対象は加入した日以降となります。
例えば、退職日から2日目に病院を受診した場合、国民健康保険の加入日によって、以下のように変わってくるのです。
- 14日以内の加入 ⇒ 自己負担分以外の医療費が支給
- 14日を過ぎて加入 ⇒ 全額自己負担
保険料はさかのぼって支払う必要があるのに、医療費は全額負担となってしまいます…
このような理不尽な目に合わないよう、国民健康保険は14日以内に加入しましょう。
月の途中で国民健康保険に加入した場合は、保険料は日割りになる?
国民健康保険料と健康保険料には、日割り計算という考え方はなく、すべて1ヶ月単位で計算されます。
したがって、3月1日に加入しても、3月30日に加入しても、支払う保険料は同じ額です。
ただし、脱退した健康保険の保険料は、「資格を喪失」した月の前月までを支払えばよいため、保険料を二重で支払うことにはなりません。
また、健康保険の被保険者としての資格を喪失する日は、「退職日の翌日」と定められています。
そのため3月31日に退職した場合は、4月1日が「資格喪失日」となり、3月までの健康保険料を支払えばOKです。
少しややこしいですが、退職日の例を取りあげると、保険料の支払先は退職日によって以下のように変わります。
- 3月30日に退職した場合:
資格喪失日が3月31日のため、健康保険料を2月分まで、国保保険料を3月分から支払う - 3月31日に退職した場合:
資格喪失日が4月1日のため、健康保険料を3月分まで、国保保険料を4月分から支払う
国民健康保険の保険証っていつもらえるの?
国民健康保険の保険証が発行されるタイミングは、各自治体によって異なります。
- 申請時に発行する自治体:
その場で国民健康保険証を受け取れます - 後日郵送で発行する自治体:
10日~14日ほどかかります
なお、国民健康保険の給付に関しては、国民健康保険の加入日より適用となりますので、保険証がなくても保険給付は受けられます。
ただ医療機関にかかる場合には、保険証という証明がないため、取り扱いが煩雑になる場合がありますので、各自治体・医療機関に確認してから、診療を受けたほうがよいでしょう。
国保を脱退し忘れて、社保との二重払いになった場合は返金してもらえる?
社会保険に加入後14日以内に、国民健康保険の脱退をしなかったため、国保と社保を二重払いにしてしまった場合は、保険料は返金(還付)されます。
すぐに市区町村役所で、脱退手続きを行いましょう。
脱退手続きを行うと、通知書と振込依頼書が届きます。(お住まいの市区町村によって、書類が異なる場合があります)
振込依頼書に、住所・氏名・指定する金融機関名などを記入して、押印して請求してください。
ただし、2年以上前の保険料は請求しても還付されません。
国保と社保の両方を、2年以上払い続けるケースは少ないかと思いますが、注意が必要です。
国民健康保険の脱退手続きは郵送でもできる?
国保の脱退手続きは、郵送でも可能な市区町村もあります。
筆者が住む地域の市役所では、確認したところ郵送でも可能でした。
お住まいの役所の国民健康保険課に連絡して、

国保の脱退手続きを、郵送でお願いしたいのですが…
上記のように伝えると、役所から書類が送られてきますので、必要書類を添えて返送するという流れです。
市区町村によっては、Webサイトで郵送用の申請書が公表されている場合もあるので、いちど確認してみましょう。
まとめ:社会保険から国保への切り替えは14日以内!期限内に手続きしよう
そこで本記事では、国民健康保険の加入・脱退の手続きについて知りたい方に向けて、
- 国民健康保険への加入・脱退が必要なケースとは
- 社会保険から国保への切り替え方
- 国保から社会保険への切り替え方
- 国民健康保険の手続きでよくある疑問(FAQ)
といったことについてお話ししました。
国民健康保険の加入・脱退の条件や、切り替え申請時の必要書類などもお分かりいただけたのではないでしょうか。
記事内でもご紹介したとおり、国民健康保険への切り替えは、期限内に行わないとかなり損をしてしまいます。
難しい手続きではありませんので、必ず期限である14日以内に申請をして、安心して病院に通えるようにしておきましょう。
セカンドゴングは40代の転職を応援しています!

当サイト(セカンドゴング)では、40代の転職に特化した転職ノウハウについて、
- 実際に40代で転職を経験した人
- 企業の採用担当・キャリアコンサルタントなど、転職活動に知見を有する人
上記のようなメンバーが数多くの記事を提供しています。
転職活動を攻略するためのコツとして、以下のようなコンテンツをご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、当サイトにノウハウを提供している転職サポーターが、あなたの転職活動をお手伝いします。
さまざまなサポートをご用意していますので、悩みがある方はお気軽にご相談ください。