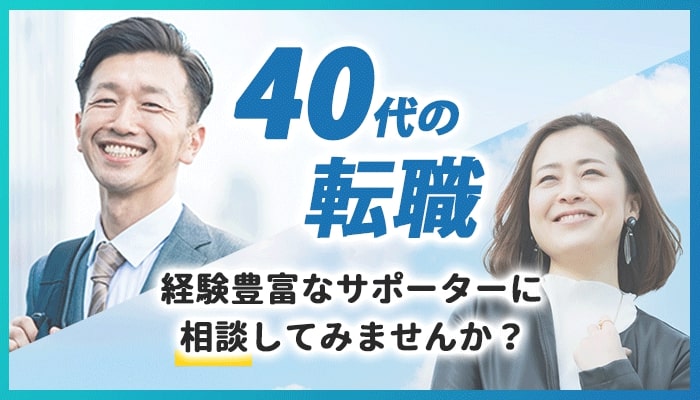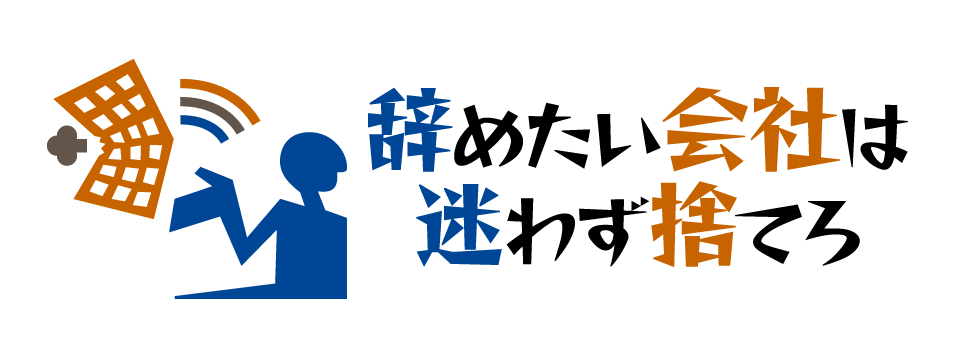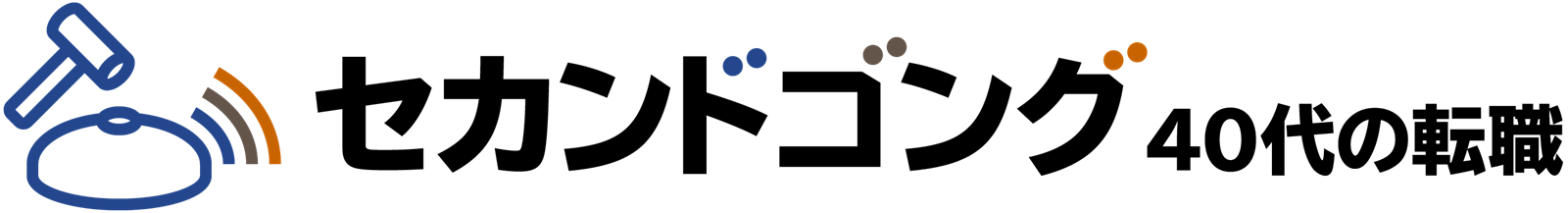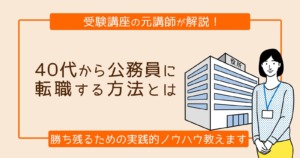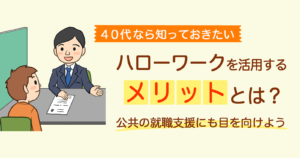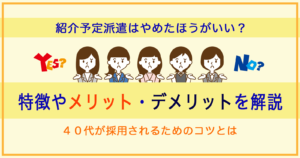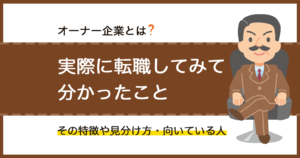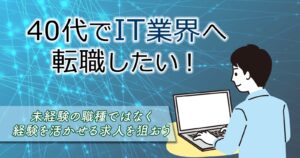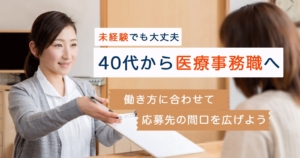40代から公務員へ転職!中途採用試験に合格するコツを徹底解説
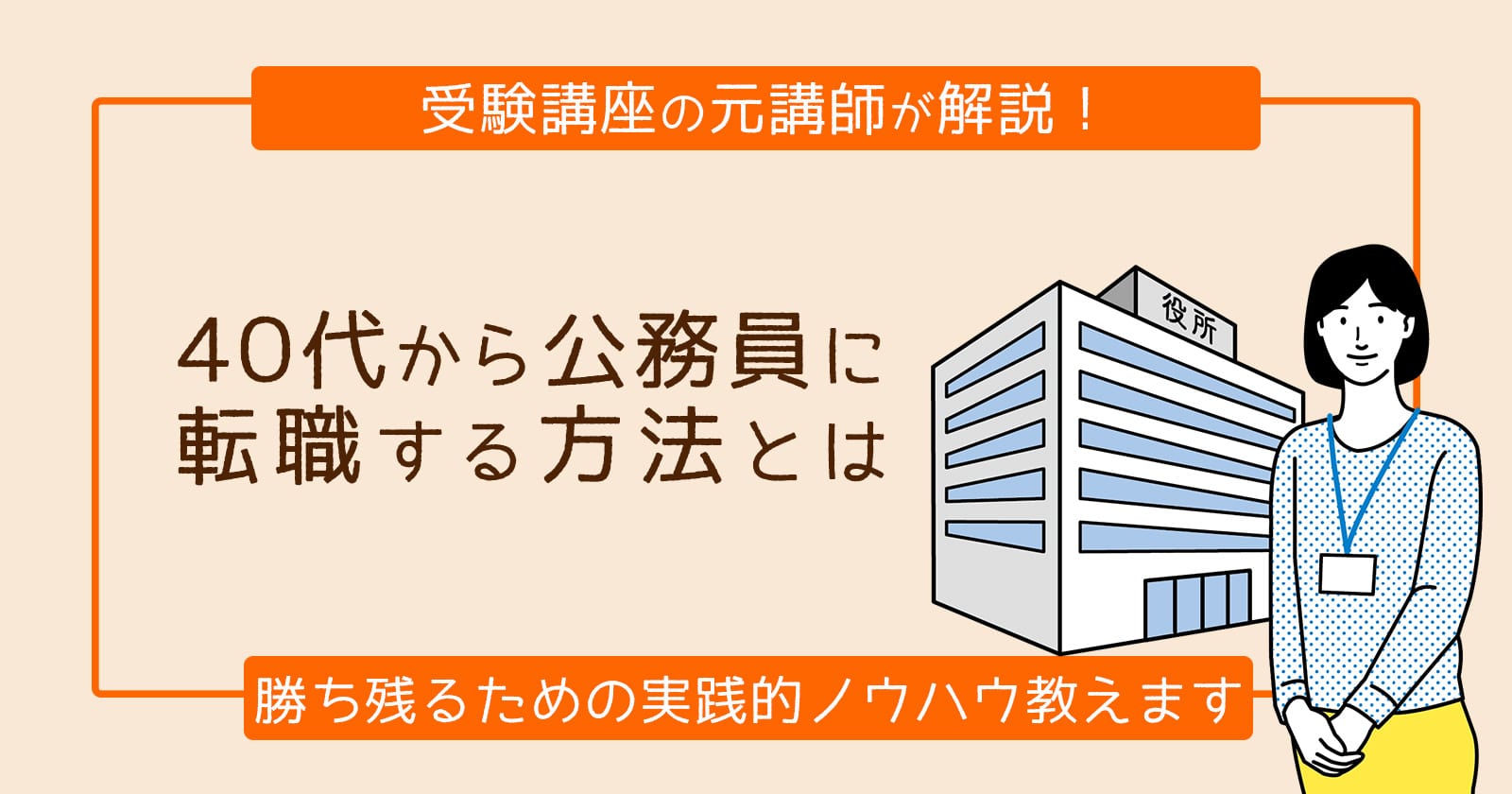
公務員採用試験は、従来は高卒・大卒の新卒や第二新卒を前提としたものがほとんどでした。
ですから、

公務員なんて、20代しか就職できないし…
このように思っている方も多いでしょう。
しかし最近では、公務員の中途採用を実施している省庁や地方自治体が増えています。
そうはいっても、この記事をご覧になるほとんどの方が、

さすがに40代は中途採用で公務員に転職できないのでは?
と疑問を持たれるかもしれませんね。
でも結論からいいますと、40代でも中途採用で公務員になることは可能です。
この記事では、40代で公務員中途採用にチャレンジしたい方に向けて、基本的な知識や具体的な対策方法などを解説しています。
社会人向けの資格専門学校で、長年にわたって公務員受験講座の講師を担当していた筆者が、余すところなくすべてをお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。
中途採用で公務員になるための基礎知識

公務員の中途採用について、

聞いたことはあるけれど、詳しくまでは知らないな…
このような方も多いのではないでしょうか?
公務員中途採用について、基本的なことをまとめると、以下のとおりです。
- 採用試験の難易度こそ高めだが、ライバルたちも条件は同じだから、それほど難しく考える必要はない
- 給与や退職金などの待遇、勤務時間などの職場環境は、他の公務員とまったく同じ
- 年功序列の組織ゆえに、中途採用なりの出世しかできない
公務員は良くも悪くも旧態依然とした体質の組織ですから、確かに中途採用なりのデメリットもあります。
その一方で、
- 安定した雇用
- 内規に従って、粛々と定められる給与や福利厚生、退職金制度など
上記のような公務員ならではの強力なメリットは、中途採用でも問題なく得られるのです。
ここでは、公務員中途採用における基本的な知識について、詳しくお話ししていきます。
公務員の中途採用を目指すのであれば、ご紹介する内容をしっかり理解したうえで、転職を検討するようにしましょう。
公務員になる難易度は? 競争率は高いのか
公務員の中途採用は、実施する国の機関、地方自治体などによって、さまざまな呼称があります。
一般的には、「社会人採用枠」とか「社会人経験者採用枠」などと書かれていることが多いです。
試験の内容と難易度について
公務員の採用試験では、以下のような試験が行われます。
- 1次試験:
公務員受験の一般教養科目のペーパーテスト - 2次試験:
小論文・面接など
面接は何回か設定される場合もあり、集団討論が実施されることも多いです。
試験の難易度だけを分析するならば、
といえるでしょう。
試験の競争率は?
公務員試験の競争率は、募集形態によっても変わってきます。
例えば、国家公務員の社会人採用枠では、全国の人から応募が集まるため、毎回かなり激しい競争率です。
国家公務員の経験者採用であれば、競争倍率は例年ほとんど30倍前後になります。
そして国家公務員の中途採用試験である再チャレンジ試験は、当時の政策の目玉としてよく知られていることもあり、150倍超になったりすることもありました。
ただその一方で、都道府県の行政職であれば、競争率は20倍~30倍程度に収まることがほとんどです。
- 選考が論文試験1本だけなど、特殊な試験科目のものは、90倍などの競争率になることもあります
市町村の行政職となれば、募集の情報が地域に限定されやすいこともあって、競争率は20倍前後で落ち着くでしょう。
競争率が10倍や20倍などと書くと、

そんな倍率では合格は難しいのでは…
こんなふうに諦めムードの人もいるかもしれませんが、どうかご安心ください。
公務員の中途採用では、ライバルとなる人たちも、みな働いている社会人ですから、
- 長らくお勉強から離れてる
- 試験を受ける対策に時間を取れない
上記のように、条件はみな同じなので、見た目の競争率ほど難しくはないというのが、筆者が実感するところです。
中途採用に年齢条件や制限はあるの?
公務員の中途採用で気を付けなければいけないのは、まずなんといっても年齢制限でしょう。
公務員を採用する側は行政機関ですから、原則として年度制で業務が動いています。
翌年4月1日時点で○○歳以下であること
上記のように年齢の指定がされていることがほとんどなので、条件をよく見てから応募するようにしましょう。
このように書きますと、

ああ、私は45歳超えているから、年齢制限でムリなのか…
このように思う方も多いかもしれませんが、早とちりはよくありません。
公務員の中途採用では、60歳まで年齢制限ナシといった募集も多くあるのです。
また、
昨年度までは年齢制限があったのに、今年度の募集では年齢制限がなくなっている
上記のようなことも珍しくありませんし、逆に年齢制限が新たに加わるケースもあります。
最初から諦めることなく、丁寧に情報収集することを心がけましょう。
公務員になった場合の配属先や仕事内容は?
採用人数も少ないですし、あまり情報が出回らないのが公務員の中途採用です。

内定後の所属部署はどうなるの?
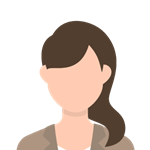
異動のローテーションはあるんだろうか…
このようなことが気になりますが、ネットで検索しても、ほとんど確定的な情報は出てきません。
ただ公務員という組織が、わざわざ中途採用をかける事情を考慮すれば、
募集するからには、何かしらの任せたい業務がある
ということは間違いないでしょう。
配属先はどうなる?
公務員というのは、一般的に「数年単位で部署をローテーションさせる」という組織ですから、最初の配属先をあまり気にしすぎる必要はないでしょう。
実際に中途採用で公務員になった人たちが、配属された部署を見てみますと、
ということがいえそうです。
仕事内容はどうなる?
多くの人が気になるのは、

配属後の仕事内容はどうなるのだろう?
ということでしょう。
これは公務員の特徴でもありますが、部署によって本当にさまざまです。
例えば、水道などのインフラに関する部署になれば、現場での業務が必ず発生します。
住民課や国民健康保険課、納税課などであれば、地域住民の方々と直に接する場面が出てきますし、クレーム対応などの要素もあるでしょう。
産業振興に関わる部署になれば、地域住民と直に接するような、接客業的な要素は減るかもしれません。
しかし、土日ごとに何らかのイベントがあるので、
- 休みが取りにくい
- 残業が常態化している
このようなことも多いものです。
公務員とは公僕という名のとおり、利害なく広く業務に携わる立場ですから、仕事環境そのものは、意外と苦労が絶えないのかもしれません。
ただこれは、民間企業でも大なり小なりあることです。
中途採用された公務員の給与や待遇は?
公務員になってからの初任給は、社会人としてこれまで歩んできたキャリアを、内規にもとづいて査定されます。
したがって、まっさらの新人扱いとなることはありません。
給与はどうなる?
中途採用の場合の給与について、人事院「国家公務員試験」のサイトでは、以下のような案内がされています。
Q.採用された場合の給与はどのように決められるのでしょうか。
採用時の俸給月額(いわゆる基本給)は、採用された方の経験年数と同程度の経験年数を有する国家公務員が受ける俸給月額との均衡を考慮して決定します。
(参考)国家公務員採用総合職試験による採用後4年の経験年数を有する係長の標準的な俸給月額 231,500円また、次のような諸手当が支給されます。
地域手当(東京特別区内に勤務する場合)…俸給月額の100分の20(月額)
本府省業務調整手当…行政(一)3級の場合、17,500円(月額)
期末手当・勤勉手当(いわゆるボーナス)…1年間に俸給等の約4.5月分このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当等の手当があります。
※ 俸給月額等は、令和2年4月1日現在の「一般職の職員の給与に関する法律」の規定によるものです。
経験者採用試験毎の給与については、受験案内に掲載していますので、ご確認ください。
出典:人事院「社会人の皆さんへ(中途採用に関する情報)」
このように、給与については一般的な公務員とまったく同列に扱われます。
肩書はどうなる?
肩書きについては、「振り出しから」という場合がほとんどでしょう。
公務員の世界では、良くも悪くも、この肩書きというのが割と重視されます。
ですから、しばらくは肩身の狭い思いをすることもあるかもしれません。
40代で転職活動をするわけですから、何かしらのデメリットが発生するのは致し方ないところ。
とくに公務員への中途採用では、肩書が振り出しからという点が40代にとって辛い部分だといえるでしょう。
ただ実際には、公務員に転職してしばらく経つと、

〇〇さんは社会人枠で公務員になったんですよね
このようなことは、ほとんどの職員から忘れられてしまいますよ。
中途採用でも出世はできる?
公務員の世界においては、
公務員として何年所属しているのか?
ということにもとづいて、職階を充てられるのが普通です。
原則として年功序列の世界ですから、出世するのも早くに組織に入った順番で決まります。
自分が「公務員として何年働けるのか」によって、未来の職階がある程度は想像できてしまうのです。
また、昇給幅もほぼ一定ですから、給与額だって想定の範囲内で推移するでしょう。
だからこそ、住宅ローンなどの申請も通りやすくなっているんですね。
公務員の人事制度とは、
ということを前提とした仕組みですから、中途採用では出世するにしても、どうしても年数の面で限度があります。
ただし、いまは激動の世の中です。
それこそ20年前であれば、公務員の中途採用制度なんて、ほとんど存在していませんでした。
就職氷河期といわれる世代の採用を、極端に絞り込んできた経緯もあって、

いまの40代の層が薄いな…
という問題点も、多くの自治体で見られる現象です。
最近では、公務員が民間のエッセンスを取り込むことを、意識している面もありますので、公務員の人事制度が今後どうなるかはわかりません。
また、そもそもの話として、いまの日本は働いてくれる人が明らかに足りていない、「人手不足」の社会構造です。
先のことまでは誰にもわかりませんから、現状だけにとらわれて、最初から出世を諦めすぎるのは、あまり賢明な判断ではないでしょう。
中途採用でも退職金はもらえる?
中途採用の公務員でも、内規に従って算定されますので、もちろん退職金は出ます。
ただし退職金とは、
という前提がありますから、40代の中途採用であれば満額は期待できません。
今のようなご時世で、安定した雇用が約束されるうえに退職金が出るわけですから、

退職金が出るだけでもありがたい…
このように考えるべきでしょう。
中小企業であれば、まともな退職金すら出ないことも珍しくもありません。
「就職氷河期世代」の公務員中途採用について
政府が推進している「就職氷河期世代支援プログラム」によって、国家公務員・地方公務員を問わずに、「氷河期世代」を対象とした公務員の中途採用が本格化しています。
当初は2019年より3年をめどにした政策でしたが、コロナ禍の影響もあって、政府は支援の2年延長を決定しました。
就職氷河期世代の支援延長 正規雇用目標2年先送り 政府、24年度30万人増に
政府は12日、バブル崩壊後に就職難だった就職氷河期世代をめぐり、令和2~4年度までの集中的な支援期間を6年度まで2年延長すると決めた。3年間で氷河期世代の正規雇用を30万人増やすと掲げたのに対し、現状では3万人増にとどまる。目標の達成が困難な見通しとなり、先送りした形だ。新型コロナウイルス感染拡大による雇用情勢の悪化が要因としている。
(中略)
政府資料によると、氷河期世代の正規の職員・従業員は、元年と2年はいずれも916万人と横ばい。3年に3万人増えて919万人となった。政府は916万人から30万人増となる946万人を目指すとしている。
出典:産経新聞(2022/5/12)
公務員への転職を考えている氷河期世代の40代にとっては、この流れはまさに追い風だといえるでしょう。
最新情報は以下のページで確認することができます。
社会人向けの採用試験について

ここでは、公務員に中途採用されるための、社会人向けの採用試験についてお話をしていきます。
公務員中途採用に関する基礎情報をご覧になって、

公務員は魅力的なんだけど、問題は採用試験なんだよなぁ…
このような印象を持っている方も多いのかもしれませんね。
では実際はどうなのか、詳しく確認していきましょう。
採用試験の難易度・競争率における実態は?
採用試験の難易度については、基礎知識のなかでも、大まかにはご紹介しました。
いずれにしても、競争倍率が10倍以上になることから、

10倍なんてとても無理なんじゃないか…
このように、非常に難しく感じている方も多いでしょう。
ところがこの競争率は、実際には見た目ほど厳しいものではありません。
試験は高校生レベルの学力テスト
公務員中途採用を、多少なりとも考えている方に伺いたいのですが、
高校や大学を卒業してからこれまでの間に、公務員採用試験で課される一般教養科目の勉強を、日々取り組んできたことがありますか?
- 一般教養科目:数的推理・判断推理・社会科学・文章理解など
上記のような質問をした場合、いかがでしょうか?
ほとんどの方はこの質問に対して、

社会人になってからは、やったことがない…
という回答になると予測されます。
試験の内容的には、高校生レベルの学力テストです。
しかも、「電卓等を持ち込まない」という前提がありますので、数学や物理のような、複雑な計算が要求される問題はほとんど出題されません。
競争率は高く見えるけど実態は?
公務員社会人採用枠の試験では、ライバルとなる人たちもみな社会人です。
はじめから公務員中途採用の試験があることを前提にして、

半年~1年くらい、毎日コツコツと対策を進めてきました!
このような人は、実際はほとんどいません。
これが、社会人向け公務員受験講座の講師を、長年にわたって担当してきた、筆者が感じている現実です。
裏を返せば、1年くらい先を見越して試験の対策を進めているだけでも、
といっても過言ではありません。
また、採用人数が少ない、実施が安定していないという特徴を逆手に取って、

合格するまで受験するぞ!
という作戦を取ることもできます。
何度かは失敗することを織り込んだうえで、コツコツ勉強を進めながら機会を伺うという考え方です。
公務員の中途採用を勝ち取るには、このやり方はかなり有効な発想といえるでしょう。
1次試験も3回目くらいになると、緊張することもなくなってきますし、ペーパーテストを効率よく処理する能力も、段違いに身についてくるはずです。
1次試験であれば、難なく通過できるようになってくるでしょう。
学歴は関係あるのか。高卒でも合格できる?
公務員の中途採用に挑むうえで、影響があるか非常に気になるのが、

公務員として採用されるのに、学歴が関係あるのだろうか?
ということでしょう。
これはある意味、日本国内で就転職活動を考えるときに、常につきまとう永遠のテーマかもしれませんね。
では、公務員の中途採用ではどうなのかというと、
学歴はほとんど影響がない採用試験である
というのが筆者の見解です。
試験で学歴が考慮される可能性は?
ペーパーテストである1次試験の合否については、学歴は関係ありません。
ある程度ちゃんと準備をすれば、誰でも公務員中途採用の1次試験を通過しているので、自信を持って関係ないといえます。
「大卒以上」などと規定がされていない公募であれば、高卒の学歴であっても、点数の上位順で普通に通過できますよ。
2次試験以降では、基本的に面接や論文試験が課されおり、
というケースがほとんどです。
仮に面接官が、全員もしくは相当な数の人が同じ学校を出ていれば、学歴が影響する可能性があるかもしれません。
しかし現実には、そんな状況になることはまずありえないでしょう。
もし面接官が7人いれば、「7人それぞれの学歴とキャリアがある」というのが普通です。
学歴だけを見て、意図的に結果をコントロールすることは難しいといえます。
学歴関係なく、徹底的な試験対策で決まる
公務員中途採用の試験対策では、面接は細部に至るまで、徹底的な対策を取ったほうが有利です。
実際の試験では、
論文試験で記述した内容と、受験者の考え方に連動性があるのか?
というところまで問われています。
また、意外なほど重要視されているのが適性試験です。
こういった試験対策が有効であり、試験の結果を大きく左右している事実をふまえると、
というのは間違いありません。
採用試験の一般的な受験の流れ

公務員中途採用の採用試験は、どのような段取りになっているのでしょうか?
ここでは、採用試験の一般的な流れについてご紹介します。
1.一次試験を受験する
1次試験では、筆記試験が行われます。
10時~11時30分、あるいは10時~12時なんていうパターンが多いですね。
公務員受験の一般教養科目※に該当する内容が、筆記試験として実施されます。
また、専門科目という名称で、社会人ならば誰でも知ってるような内容で、一般常識を問われる試験が課される場合もあります。
会社法 / 民法 / 不動産 / 簿記会計 / 政治経済 / ITなど
上記のような幅広い分野から、それぞれ簡単な問題が出題されるケースがほとんどです。
一般教養科目・専門科目ともに、一見すると難しく感じるかもしれませんが、受験を前提として対策を取っていれば、難しい問題はそれほど多くありません。
2.二次試験(小論文)
2次試験でよく課されるものが小論文試験です。
お昼の休憩時間をはさんで、13時30分~15時などのスケジュールで、実施されることが多くなっています。
論文試験に対しては、

どうしても苦手意識がある…
このような方も多いのですが、じつは対策はそんなに難しくありません。
2次試験に進めるレベルになってくると、実際に面接をする前提で、試験対策をしているはずです。
面接対策として、日本社会や地方自治体が抱えている様々な諸問題について、時事を押さえながら、

自分なりの考え方や主張は話せるんだけど…
というレベルに達しているのではないでしょうか?
論文試験では、1時間半の試験時間のなかで、800字程度の文章を書くことがほとんどです。
あらかじめ準備していた素材を、誤字脱字なく文章化すれば問題ありません。
お勉強というよりは、
事前の準備が、どれくらい丁寧にできているのか?
ということが問われる内容です。
周囲が難しがっているあいだに、
- 新聞を購読する
- 時事問題で定番のテキストを読んでおく
上記などの対策を取っていれば、心配には及ばないでしょう。
3.二次試験(面接)
公務員中途採用の採用試験で、最も難関といえるのが面接試験です。
面接試験には、個別面接・集団面接と2つのパターンがありますが、どちらも気を付けるべきポイントに大きな差はありません。
公務員中途採用では、
- 民間企業で培ってきたキャリアが、公職でどう活かされるのか?
- キャリアの半ばで、公務員を志望するのはなぜか?
上記のような必然性をとにかく追求されます。
当然ながら、

安定した職業なので志望しました
このような本音を語っていては、採用には至りません。
新卒や若手想定の一般的な公務員試験で出されるような、面接の定番質問をしっかり抑えつつ、中途採用ならではの切り口でも、対策を練っておく必要があります。
採用試験における面接対策が、非常にボリュームがあるうえに、難しい部分といえるでしょう。
採用試験の対策方法【中途採用の場合】
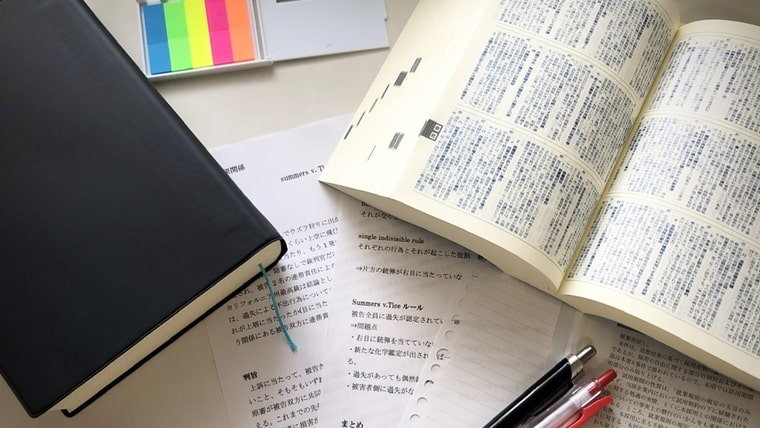
インターネットがこれだけ普及した今でも、公務員中途採用の情報は非常に少ないです。
ただ、思っているほど難しい試験ではありませんから、ぜひ積極的にチャレンジしてみましょう。
ここでは、社会人向けの資格専門学校で公務員受験講座の講師を担当してきた筆者が、長年の講師経験で得た現場ノウハウをご紹介します。
細かく掘り下げると、読み切れない量になってしまいますので、ガイド的な内容となりますが、ぜひ参考にしてください。
ご紹介する内容に沿って準備をしていただくだけでも、1年後には1次試験をクリアして、面接試験で合否の最低ラインを競うくらいにはなれるはずです。
【筆記試験】独学で勝ち残ることも可能
1次試験の勉強内容と対策方法については、独学でも可能です。
書店で販売されている定番の書籍を3回ほど解いておくと、地方自治体の社会人採用枠試験では、かなり有利になるでしょう。
まったく同じ問題が出ることはないですが、同じ発想で同じ知識・公式を使う問題が頻出するからです。
対策をしておく科目は、一般教養科目の出題範囲で5割を占める、
数的推理、判断推理、社会科学
これらから優先的に取り組んでおきましょう。
▼公務員中途採用 筆記試験の学習書籍はこちら▼
【小論文試験】新聞の定期購読が効率的な対策
2次試験の時事対策・論文対策については、
毎日欠かさずに新聞を読んでおく
ということを心がけてください。
論文については付け焼刃では対策になりません。日頃から新聞を読むくせをつけ、時事トピックに関する情報収集に努めましょう。
とくに受験予定の地方自治体エリアの地方紙と、日本経済新聞を併読しておくと、公務員試験でカバーしておくべき論点は、ほぼ網羅することができます。
新聞は定期購読することが、もっとも効率的な対策です。
しかし、短期間で合否を争うレベルに持っていくのであれば、公務員受験対策では定番の書籍ともいえる、資格試験研究会の「速攻の時事」を1冊読了しておきましょう。
また、文章を書くことが苦手な人は、意外と多いものです。

たしかに文章を書くのは苦手かも…
もしこのように思うのであれば、論文試験対策の書籍などを熟読して、試験レベルの文章は書けるように、対策を進めておきましょう。
実際の試験では、800字~1200字程度の文字数の記述が求められますが、出題されるテーマについては、わりと定番化したものが軸になっています。
必要以上に恐れることなく、少しづつ準備をして試験に挑みましょう。
【面接試験】専門学校や転職エージェントの模擬面接を活用
公務員中途採用の採用試験において、もっとも難しいのは面接対策です。
面接試験がないという公務員採用試験は、恐らく存在しないでしょう。
それにもかかわらず、面接対策を十分にやっている方は非常に少ないのです。
面接対策については、自分ひとりで対策するのには限界があります。
- 公務員専門学校の対策講座を受けてみる
- 転職エージェントなどに登録して、面接対策の専門家に指導をお願いする
上記のような対策を取ることをオススメします。
面接試験の具体的なノウハウについては、40代が転職面接で必ず聞かれる5つの質問でご紹介していますので、あわせてご確認ください。
公務員面接試験でのお約束とは
社会人経験者であれば、面接で普通は変なミスはしないでしょう。
しかし、公務員受験での「お約束」については、意外と知らないことが多いかもしれません。
- 入室時のノックが2回だと大幅減点されるので、ノックは必ず3回
- 集団面接では、自分が答える時よりも、他者が答えているときの態度に点数が重く付けられる
- 面接時に笑顔が出せるかどうか(とくに市役所・町役場など)
- 公と民の違いをどう捉えているのかという定番質問
- 「それは公でなくてもできるよね」という圧迫質問
- 中途採用では自身のキャリアと照らし合わせた必然性を問われる
上記のような、公務員の面接試験で問われる質問内容や、立ち振る舞いについての基本情報は、あらかじめ押さえておく必要があります。
このあたりも地道に準備を進めておきましょう。
一般教養課程の勉強だけでは不十分! 二次試験の対策が重要
ここまでお話ししたように、1次試験を突破すると、もれなく論文試験や面接が課せられます。
2次試験で実施される内容は、筆記試験が中心となる1次試験と比較しても、

かなり対策が取りづらいな…
と感じるものばかりでしょう。
ただ、これらを通過しないことには、公務員の中途採用試験に合格して、念願となる公務員への転職を果たすことはできません。
1次試験をいちど通過できると、以後は自治体・機関を問わず、連続して1次試験を通過できるようになってきます。
公務員中途採用を勝ち取るためには、2次試験の対策がとくに重要になってくるので、しっかり対策しておきましょう。
40代が公務員試験に挑むうえでやっておくべきこと


公務員中途採用の試験に勝ち残って、転職活動を終わらせたい!
このように考えている中高年の方は、決して珍しい存在ではありません。
しかし一方で、競争倍率の高さがついて回るのが、公務員中途採用の特徴でもあります。
ここからは、激しい公務員試験へ本気でチャレンジする方のために、試験対策を進めながら、並行して取り組んでいただきたいことをお話しします。
ポイントとなってくるのは、
あなたの転職活動の最終目的は、本当に公務員になることですか?
このような本質的な問いかけです。
公務員中途採用の募集情報を調べる方法
- 公務員採用試験が30~40代の社会人経験者向けに実施されている
- 公務員の中途採用を行っている
まずこのようなこと自体が、一般的な認知度としてはまだまだ低いですから、情報収集は困難を極めます。
最終的な内定を勝ち取るためには、たとえ困難であっても、
採用試験の情報を、いかに素早くキャッチしていくか
ということが、非常に重要になってくるでしょう。
各都道府県にあるような有力な公務員専門学校であれば、地域内の採用試験についての情報は揃っているはずです。
公務員専門学校の公式サイトで、よく情報提供がされていますので、まずはこれらをチェックしてみましょう。
また、「公務員試験情報こむいん」では、全国の国家公務員・地方公務員の採用試験情報を集約しています。
もちろん「すべてを完全に」ではないのですが、網羅している精度が非常に高いので、公務員中途採用で転職を狙うならば、こちらも定期的にチェックしたいサイトです。
採用試験情報をもれなく押さえていくことで、受験する機会が増えていきますから、1次試験突破の可能性が高まります。
実際に会場まで足を運ぶ受験回数も重ねることで、場慣れもして試験問題にも慣れてくるはずです。
1年後には、かなりの確率で1次試験を突破できるようになってくるでしょう。
採用試験で情報収集したものを管理・活用する
公務員中途採用の採用試験に何度もチャレンジしていると、採用試験にまつわるさまざまな資料が蓄積されていくはずです。
公募チラシや募集要項はもちろん、実際に応募をするたびに、応募用紙(エントリーシート)をひと揃い作ることになるでしょう。
公務員中途採用を目指す方ならば、ぜひこれらの資料については、
ひとつのバインダーにまとめて、ファイリングしておく
ということをおすすめします。
仕事で忙しいなかでも、採用試験のためにやるべきことは多いです。
内定を勝ち取るためには、物理的にかけられる時間数が要求されてくるでしょう。
また、エントリーシートは合格するまで何度も書き上げる書類ですから、回数を重ねるごとに、内容を改良していく必要があります。
それまでに作り上げてきた応募に関する資料は、しっかり整理して揃えておいて、何度も見直していきましょう。
非営利団体や半官半民団体、民間企業についても転職先として視野に入れる
そもそも論ではありますが、公務員中途採用の試験に挑む本質的な意味は、一般的な資格試験とは異なって、
ということでしょう。
たとえば、簿記や国家資格などの資格試験であれば、最終的に試験に合格することで、「資格」という能力を証明する証が得られます。
また、合格するまでの学習期間のあいだに、実務的な知識体系を習得しているはずです。
ところが、公務員中途採用を狙う受験生は、公務員の採用試験対策以外に、なにか活用できるスキルを得られるわけではありません。
転職活動であることを前提とするならば、ただやみくもに公務員試験のみを受験するのではなく、
- NPO法人
- 医師会、業界団体などの非営利団体
- 商工会議所・商工会・独立行政法人など
上記のような半官半民団体の受験や、民間企業への転職も同時に視野に入れておきましょう。
【FAQ】40代の転職でよくある疑問・質問にお答えします
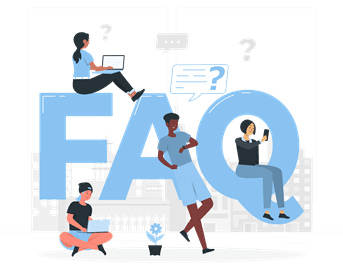
ここでは、40代の転職でよくある疑問・質問にお答えします。
ぜひ参考にしてください。
-
仕事・生活のなかでやってきたことを、的確に言語化して表現することで、企業側に「強み」として認識されるものは誰にでもあります。
以下の記事を参考にして、これまで自分がやってきたことを、スキルとして言語化してみましょう。
-
結論からいうと、40代の転職が厳しいのは本当です。
ただし、転職に成功している40代がたくさんいるのも事実。
40代の転職におけるノウハウをしっかり学べば、転職することはけっして不可能ではありません。
十分な準備をしたうえで、転職活動に挑みましょう。
-
40代女性が長く続けられる仕事に出会うためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 40代女性の採用が多い転職先を知る
- 転職先に「長く働ける環境があるか」を把握する
- 歴史のある、経営が長い企業を選ぶ
経験豊富な40代女性だからこそ、活躍できる職場がたくさんあります!
「将来性」「安定性」「柔軟性」を意識して、40代女性に実績のある転職エージェントを活用しながら、理想の仕事を見つけましょう。
-
40代の転職活動でみじめな思いをする人は、以下の理由で失敗しているパターンが多いです。
- 不採用続きで転職活動がうまくいかない
- 転職したことを後悔している
ただ、すべての方がみじめな転職活動をしているわけではなく、40代で転職を成功させている人もたくさんいます。
失敗を回避するためのポイントは、事前準備をしっかりおこなうこと。
「スタートラインで転職活動の成否が決まる」といっても過言ではありません。
-
40代が新しい職場に馴染めないのは、珍しいことではありません。
職場に若い世代が多ければ、仲間として認識してもらえないのが普通ですから、自分から馴染む努力をすることが重要です。
ただし、本人の努力だけで改善が難しい場合は、再転職も視野に入れましょう。
スキル・キャリアがない場合はどうすればいい?
40代転職の現実が知りたい。本当に厳しいのですか?
40代女性が、一生出来る仕事に出会うためにはどうすればいい?
40代で転職するとみじめになる?
新しい職場に馴染めないので辞めたい…
おわりに:40代で公務員中途採用へチャレンジする方へ
公務員中途採用へのチャレンジは、一般的に1年~3年ほどの時間がかかります。
その間は、転職活動そのものが完了するわけではないところが、公務員への転職活動の難しいところでしょう。
40代の転職であれば、1年1年が大事な勝負です。
本当に数少ないチャンスが来る「その時」を待って、タイミングよく自分のキャリアを切り拓いていく必要があります。
公務員の社会人採用枠試験に合格するために、

しっかり準備を進めていくぞ!
という覚悟と志が、何よりも大切になってくるでしょう。
ただし、40代であれば「1年」という時間の単位は大変貴重ですから、公務員中途採用だけに的を絞って、転職活動するのは危険です。
転職を果たす確度を上げるためにも、民間企業への転職という可能性も捨てずに、情報収集と自己スキルの向上に努めてください。
セカンドゴングは40代の転職を応援しています!

当サイト(セカンドゴング)では、40代の転職に特化した転職ノウハウについて、
- 実際に40代で転職を経験した人
- 企業の採用担当・キャリアコンサルタントなど、転職活動に知見を有する人
上記のようなメンバーが数多くの記事を提供しています。
転職活動を攻略するためのコツとして、以下のようなコンテンツをご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、当サイトにノウハウを提供している転職サポーターが、あなたの転職活動をお手伝いします。
さまざまなサポートをご用意していますので、悩みがある方はお気軽にご相談ください。