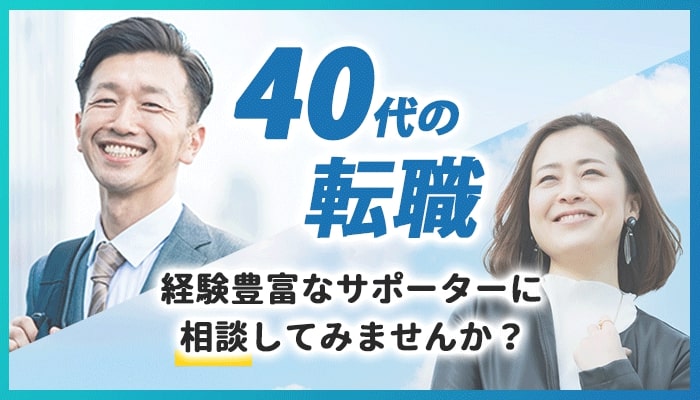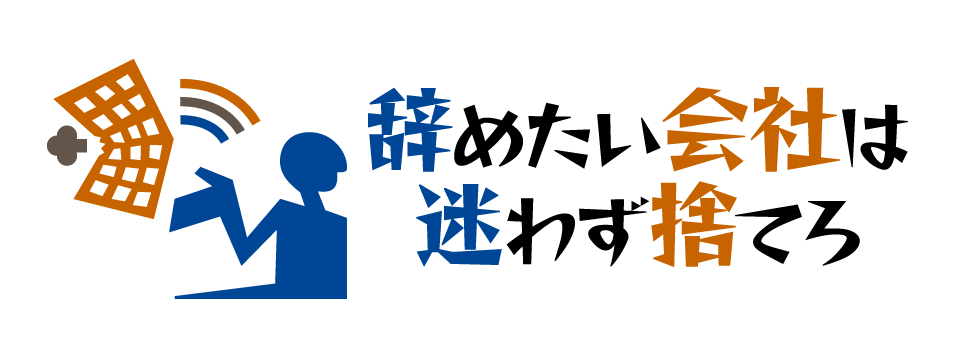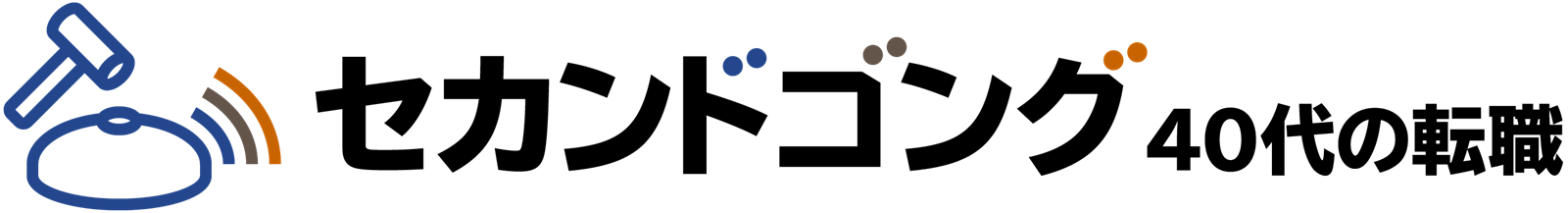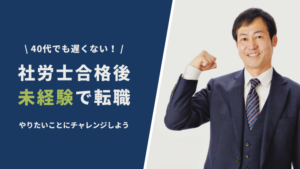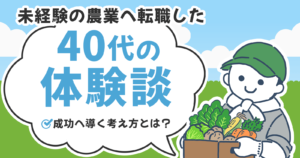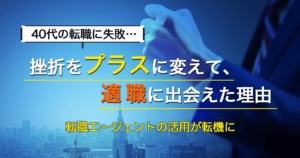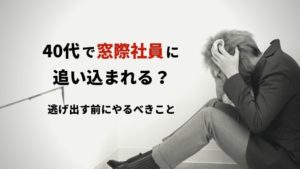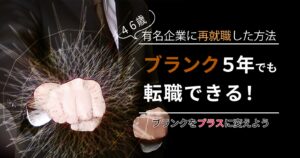社労士合格後に転職!40代男性が未経験で就職できた方法とは
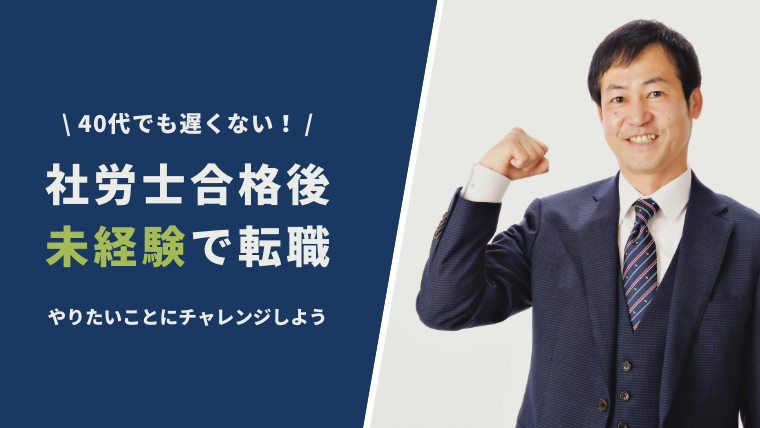
社会保険労務士の資格に興味はあるけれど、

なんだか難しそうだし、働きながらでも取れるのかな…
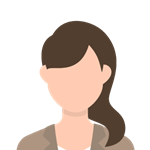
資格を取ったところで、40代からでも転職できるの?
こんなふうに悩んでいる方はいませんか?
大丈夫です!
社労士は働きながらでも合格できますし、転職にも十分役立ちます。
なんだったら、資格を持っていなくても、社労士事務所に転職することは可能です。
筆者も会社員をしながら勉強して、45歳で社会保険労務士の資格を取得。
そして資格取得後には、業務未経験で社労士事務所へ転職できました。
社会保険労務士というのは、いろいろな働き方ができるのが魅力です。
勉強するのはもちろん大変ですが、苦労は報われると信じて、合格を目指しましょう!
この記事では、40代の未経験で社労士に転職した筆者が、社労士として転職するためのポイントについて解説しています。
筆者の体験にもとづいて、わかりやすくお話していますので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたの悩みを解決するヒントにしてください。
社会保険労務士は働きながら取れる資格です

社労士の資格は難関と思われていますが、じつは働きながらでも十分に合格できる資格です。
実際に筆者も、会社員をしながら試験に合格しました。
合格者のデータを詳しくみていくと、
多くの会社員が働きながら合格している
ということがわかります。
合格者の60.4%は会社員
社会保険労務士の合格率は、ここ数年でみると、6%台から7%台で推移しています。
◆社会保険労務士試験合格者の推移
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |
| 2020 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |
| 2019 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |
| 2018 | 38,427人 | 2,413人 | 6.3% |
| 2017 | 38,685人 | 2,613人 | 6.8% |
この数字だけみると、

仕事を辞めて勉強しないと、合格は難しいのでは…
このように思う方もいるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
◆社会保険労務士試験合格者の職業別構成
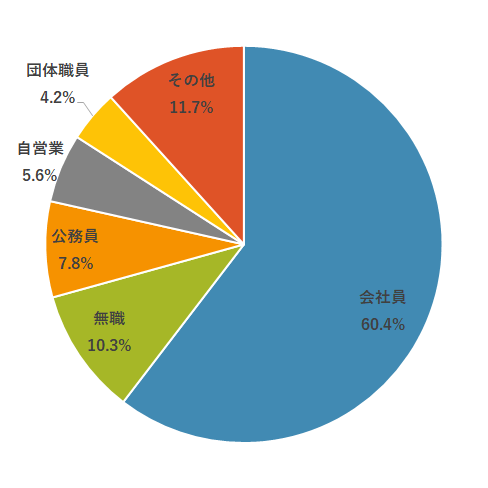
上記の合格者データ(令和3年度)を見てみると、合格者のうち60.4%が会社員です。
◆社会保険労務士試験合格者の年齢別構成
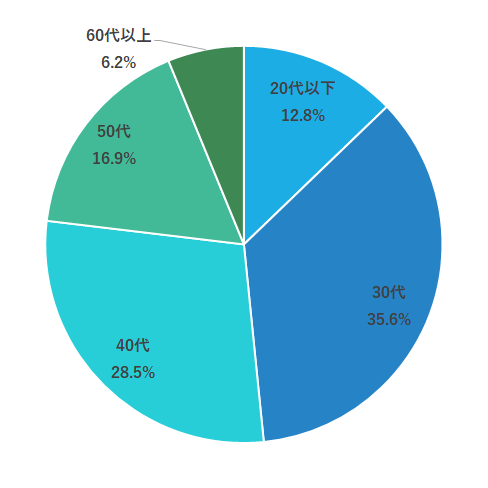
年齢別で見ても、40代が28.5%、30代が35.6%となっているように、
働きながら合格を勝ち取った人が非常に多い
ということがわかります。
確かに簡単に合格できる試験ではありませんが、あきらめずに正しい方法で学習すれば、必ず合格できる試験だといえるのです。
合格率にはトリックがある
じつは合格率には、トリックがあります。
上記で合格率を計算するのですが、実際には受験者数のすべてが、合格ラインに立っているわけではありません。
記念で受験している人や、単なる腕試しで受験している人も、受験者数のなかに相当数が含まれています。
合格率という数字に惑わされず、
合格に必要な知識を身につけるために、どうすればよいか?
ということに意識を向けるようにしましょう。
社会保険労務士として働く魅力・メリットは?

この記事を読まれているのは、社労士への転職を検討しているという方が多いでしょう。
社会保険労務士とは、時代の後押しもあるなかで魅力的な業務が多く、働き手としての可能性が広がる仕事です。
ここでは、社労士として働くことの魅力やメリットについて、実際に社労士へ転職をした筆者の目線でお話しします。
働き方改革が社労士のニーズを後押ししている
社会保険労務士のおもな業務は、
企業の人事や総務部門のお手伝いをする
ということ。
社労士事務所では、給与計算から人事・労務に関するコンサルティングまで、幅広い業務にあたっています。
いまでは「働き方改革」という言葉をよく聞きますよね。
企業は残業の削減などに躍起になっており、社労士が活躍できる場面が増えています。
社会保険労務士は、数ある士業の中でも、「人」に関するエキスパート。
お客様である企業の「人」に関する悩みに、ダイレクトに応えられる職種といえるでしょう。
コンサルティング業務が熱い!
社会保険労務士というのは、

残業を削減するために、業務の生産性を上げたいのだが、どうすればいいのだろう?

従業員のスキルアップや定着を図るために、どのような人事評価制度を構築するべきかな…
上記のような企業の悩みごとに対して、コンサルティングを提供しやすい位置にいる仕事です。
実際に、企業からの問い合わせは年々増えています。
AIや外国人労働者の参入が懸念されていますが、人手不足の状況は簡単に解決できる問題ではありません。
「人材の採用・定着」の問題は、これからも企業のニーズであり続けるでしょう。
社労士は「独立する・しない」も自由に選べる
転職というと、「会社から会社へ」というイメージが一般的ですよね。
実際に、社労士として最初の転職は、
社労士事務所への就職する
というのが一般的でしょう。
もちろん、社労士の資格を取って、
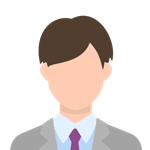
業界未経験ですが、独立してがんばります!
という方もたくさんいます。
しかし、まずは社労士事務所に就職して、ひと通りの業務内容を覚えることも、選択肢のひとつでしょう。
社労士事務所に就職したあとは、
- 定年になるまで、そのままスタッフとして勤め続ける
- ゆくゆくは独立する
上記のように、働き方を選ぶことができるのも、社労士の魅力であります。
実際に、社労士の登録方法は、
この3つの種別があり、すべての社労士がいずれかの種で登録しているのです。
自分でやりたいことがあるなら独立しよう
筆者はいま、勤務社労士として働いています。(追記:2020年1月に独立開業しました!)
スタッフとして働くのも、やりがいはあるのですが、

もっとダイレクトに世の中の役に立ちたい!
という思いがあるので、いずれは独立しようと思っています。
社労士の良いところは、弁護士や税理士と同じく、顧問契約を取りやすい職種であることです。
もちろん、顧問契約をいただくことは、易しいことではないのですが、
- 毎月安定した収入がある
というのは、事業主として大きなメリットとなります。
いまのご時世、ダブルワークも主流になりつつありますので、
社会保険労務士 + 〇〇
このような働き方もあるでしょう。
自分のやりたいことを仕事をするには、どうすれば良いかを考えていくことで、あなたの可能性はさらに広がるかもしれません。
社労士事務所の求人における特徴とは
別の業界から、社労士事務所に転職したいと思った場合に、

社会保険労務士の資格がないと、転職ができないのでは?
このように思われる方もいるかもしれませんね。
でもそんなことはありません。
事務所にもよりますが、未経験や資格なしでも転職できる場合があります。
「未経験者歓迎」で募集しているところもある
実際に、社労士事務所の求人欄を見てみると、
- 未経験者歓迎
- 社労士資格勉強中の方歓迎
このような記載がある求人をよく見かけます。
裏を返せば、経験者(社労士合格者含む)だけでは、
人手が足りていない事務所が存在する
ということです。
ただ、何の知識もない状態で飛び込むのは、転職した後に苦労するでしょう。
社労士事務所は大企業とは違って、研修制度などが十分に整っていない場合も多いです。
当然ながら法律用語も多いですから、

資格を取るつもりで事前に勉強しておこう…
というスタンスをおすすめします。
そうやって勉強しておくと、面接の際にアピールすることも可能です。
資格がなくてもおこなえる業務はある
社労士事務所では、顧客企業における、
- 給与計算
- 社会保険手続き
上記の業務などを、メインに行なっているところが多いです。
しかしこれらの業務は、すべてを社会保険労務士が行うわけではありません。
もちろん最終的には、所長である社労士の名前で仕事を完成させますが、
入力作業などのアシスタント業務は、無資格でも問題ない
というのが実情です。
志望動機が重要視される
あなたは、なぜ社労士事務所に転職したいのか、志望動機を整理できていますか?

人事労務に興味があり、将来的には独立したい…
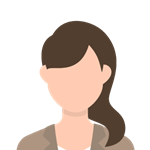
今まで総務で給与計算などをしていて、キャリアアップをしたい!
上記のように、さまざまな理由があるでしょう。
資格の有無に関わらず、
自分は社労士業界で何をしたいのか?
ということを、よく考えておくことが重要です。
面接では、
 面接官
面接官あなたはウチの事務所で何がしたいのですか?
必ずこのような質問をされますよ。
社労士事務所が未経験者を歓迎している理由

前述したように、社労士事務所の求人欄には、「未経験者歓迎」と書いてある求人をよく見かけます。
ただ、「未経験者でも歓迎」するのには、当然ながら何らかの理由があるはずです。

なぜそこまでして、求人を募集しているのだろうか?
ということを見極める必要があります。
事務所の人手が不足している
企業の人手不足を取り上げているニュースをよく見かけますよね。
それは、社労士事務所も例外ではありません。
人気の社労士事務所であれば、常に仕事が舞い込んできますから、求人をかけてどんどん規模を大きくしているのです。
このような事務所では、仕事はきっと大変でしょう。
しかし、そのトレンドに乗ることで、
未経験でもしっかりとした業務経験を積むことができる
というメリットもあります。
人の入れ替わりが激しい
ひんぱんに求人を出している社労士事務所のなかには、

人が辞めていくから、募集をかけるしかない…
このような場合もあります。
社労士事務所には、激務である会社が割と存在しているのです。
そういった事務所では、仕事量に対してスタッフの数が足りておらず、常に大量の仕事を抱えて働いています。
せっかく新人のスタッフが入所しても、
- 研修制度が整っていない
- 誰も教えるヒマがない
常にこのような状態でしょう。
誰にも仕事をロクに教えてもらうことができないため、すぐに辞めてしまう悪循環となっているのです。
トップのキャラクターが影響している
社労士事務所は、スタッフ数名~十数名までの小規模な事務所が多いです。
したがって、トップである所長のキャラクターが、事務所の運営に色濃く出ている場合があり、
所長との相性が合いそうかどうか?
上記が勤務先を選ぶうえで重要な要素です。
スタッフはいい人が多くて仕事をしやすい事務所なのに、
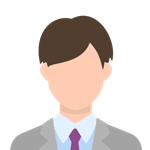
どうしても所長とは合わなくて、長続きしない人が多いんだよね…
このような話も、実際にはちらほら耳にすることがあります。
なぜ40代から社会保険労務士を目指したのか?

ここでは、筆者がなぜ40代から社労士事務所へ転職しようと考えたのか、その経緯についてお話しします。
会社で総務を経験したことで、社労士という仕事を知る
社労士事務所へ転職する前は、筆者は製造業で総務を担当していました。
ですが、最初から総務だった訳ではありません。
元々は生産管理を担当していましたが、総務を兼任することになり、

「社会保険労務士」っていう仕事があるのか…
そこではじめて存在を知ることになったのです。
それまでは、社労士にはまったく縁がありませんでした。
社労士の勉強をしようと思ったのも、総務業務に必要な知識を得るため。
社労士事務所へ転職をしようなんて、当時は考えもしませんでした…
試験に合格後、社労士事務所への転職を考えるように…
社労士の試験勉強を進めていくにつれて、社会保険労務士の仕事に興味を覚え始めました。
そして試験に合格した頃には、

人事労務の世界をもっと知りたい
このように思うようになったのです。
さらに、社労士の活動に関するセミナーなどへ参加しているうちに、

社労士事務所に転職して、本格的に仕事をしてみたい!
上記のように考えるようになりました。
そして試験合格から約半年後、ついに退職願を出すことなったのです。
40代で社労士への転職活動をしてみて学んだこと

40代で社労士事務所への転職活動をしてみて、学んだことや気付いたこともたくさんありました。
ここでは、実際に活動してわかったことをお話しします。
最初は不安だらけでした…
転職すると決心したのは良かったのですが、

社労士の資格を取ったとはいえ、業界未経験の40代半ばの男を、受け入れてもらえるのだろうか…
このような心配はありました。
また、かりに転職に成功したとしても、

妻と息子(6歳)を養うことはできるのかな…
と不安な気持ちでいっぱいだったのです。
ただ、仕事は辞めずに続けていたので、「ダメで元々」という感じで、まずは一歩を踏み出すことができました。
行動を起こせば、意外と何とかなる
結論から申し上げると、
不安に思っていたことは、すべて思い過ごしだった
というのが実際のところです。
妻には、自分のやりたいことを説明すると、

頑張ってね、応援するから!
このようにすぐに理解をして、応援をしてくれました。
もちろん不安を感じることはあったでしょう。
ただ、筆者がつまらなさそうに会社に行っているのが、妻は気になっていたようで、筆者が転職をすることに賛成してくれました。
肝心の転職活動については、開始してからわずか1ヶ月で、内定をいただくことに成功!
結果としては、充分といえるのではないでしょうか。
なぜ未経験でも社労士に転職できたのか?
いま振り返って考えてみると、面接のときに、
自分のスキルではなく、ビジョンを語ったこと
これが内定をいただけた要因ではないかと思います。
たとえサラリーマンを数十年経験していて、社労士試験にも合格したといっても、社労士業界においては素人同然です。
ですから、これまでのサラリーマンスキルをアピールしたところで、何の役にも立たなかったでしょう。
これまでのキャリア・経験をアピールするよりも、
- 自分がこれからやりたいこと
- 転職して成し遂げたいこと
上記について熱く語ることで、
 面接官
面接官この人となら、一緒に働いてみたいな
面接官にこのように思ってもらえた気がするのです。
未経験で社労士事務所に転職する方法

ここでは、筆者と同じように未経験で社労士への就職を考えている方に、転職するために押さえておきたいポイントをご紹介します。
転職が決まるまで仕事を辞めないこと
なんだか矛盾しているようですが、もし可能であれば、
今の仕事を続けながら、転職活動する
というのがおすすめです。
退職してから、じっくり転職活動する方法もありますが、万が一思うように進まない場合に、生活のことを考えて焦りが出てしまうのです。
その結果、

不本意だけど、この会社で妥協するしかない…
こういったことになりかねません。
今の収入を確保しながら転職活動をすることで、じっくり冷静な判断で、転職先を見極めることができます。
もちろん仕事をしながらの転職活動はラクではありませんが、
- 現職であるほうが、無職の人よりも選考で評価されやすい
というメリットもあるのです。
働きながら、焦らずじっくりと取り組みましょう。
社労士へ就職する理由をよく考え、事前準備をしておく
転職活動を始めるときには、
- 何のために転職するのか?
- なぜその会社を受けるのか?
事前にこれらをよく考えておくことが重要です。
40代ともなると、就職活動や転職活動から長らく離れているので、

面接ってどんなだったかな?
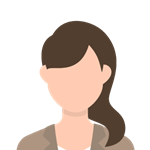
職務経歴書の書き方がよくわからない…
このような人もいるでしょう。
転職に関するサイトや関連書籍などを読んでおくなど、事前準備はきっちりしておくことをオススメします。
40代が転職で準備するべきことは、40代が転職活動で準備するべき5つのポイントでご紹介していますので、あわせてご確認ください。
転職に求めるのは「収入」か「生きがい」か?
筆者の場合は、未経験の業界に転職したので、収入は前職よりも20%ほど下がりました。

もちろんこれからガンガン稼いでいくつもりです!
自分のなかでは、生活レベルを落としてでも、「自分のやりたい仕事」を選んだのです。
もちろん妻には、申し訳ないことをしたと思っています…
ですが、これからの人生を自分のやりたくない仕事に費やしたくない。
たとえ生活レベルが下がっても、
自分のやりたい仕事をして、生きがいを得たい
という思いが強かったのです。
いまは新しいことへの出会いばかりで、覚えることも多くて大変ですが、前職にはなかったワクワク感に囲まれて、充実した毎日を過ごしています。
転職で何を得たいかは人それぞれですが、もし今の仕事に少しでも引っかかるものがあるのでしたら、

自分の生きがいは何なのか?
この問いに対して、じっくりご自身向き合ってみるといいでしょう。
できれば入社前に、「事務所見学」をやっておこう
入社を決める材料は、できるだけ多く確認しておくべきです。
可能であれば、入社前に「事務所見学」をすることをおすすめします。
事務所の雰囲気などは、面接では分からないこと多いですから、

事務所見学をさせていただくことは可能でしょうか?
と申し出てみましょう。
業務で扱うものが個人情報であることが多いので、スタッフの隣に座って見学することは難しいかもしれません。
部屋の隅に座ってでも、事務所の雰囲気をつかむことに集中しましょう。
- 所長とスタッフがどのように関わっているのか?
- スタッフ同士がどのような会話をしているのか?
- 電話の応対の仕方などで気づいたこと
こういったことをメモしておき、入社するかどうかを決める判断材料のひとつにしてください。
ただし、事務見学を断られてしまった場合は、いさぎよく引き下がるようにしましょうね。
まとめ:40代からでも未経験で社会保険労務士に転職できる!
今回は、社会保険労務士の転職について、現役社労士が詳しくお話ししました。
社労士事務所への転職は、資格がなくても可能です。
40代で未経験で入所して、働いて経験を積みながら、社労士資格の取得を目指すこともできます。
ただし、求人欄に「未経験歓迎」の文字がある場合は、
なぜ未経験者でも大丈夫なのか?
という理由について、冷静に見極めましょう。
面接などの限られた機会のなかで、事務所の雰囲気を掴むのは大変かもしれません。
しかし、自分がこれから働く場所なのですから、しっかりと確認しておくべきです。

資格を取りたいので、社労士事務所へ転職したい
このように考えている方は、むしろ「いまの職場に留まって勉強する」ことをおすすめします。
慣れない仕事のなかで勉強するよりも、慣れた仕事で自分の時間をコントロールしながら、勉強時間を確保する方が合理的です。
社会保険労務士は独立開業も目指せますので、人生の選択肢を増やす意味でも、ぜひ資格合格と転職を目指してチャレンジしてみましょう!
セカンドゴングは40代の転職を応援しています!

当サイト(セカンドゴング)では、40代の転職に特化した転職ノウハウについて、
- 実際に40代で転職を経験した人
- 企業の採用担当・キャリアコンサルタントなど、転職活動に知見を有する人
上記のようなメンバーが数多くの記事を提供しています。
転職活動を攻略するためのコツとして、以下のようなコンテンツをご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、当サイトにノウハウを提供している転職サポーターが、あなたの転職活動をお手伝いします。
さまざまなサポートをご用意していますので、悩みがある方はお気軽にご相談ください。